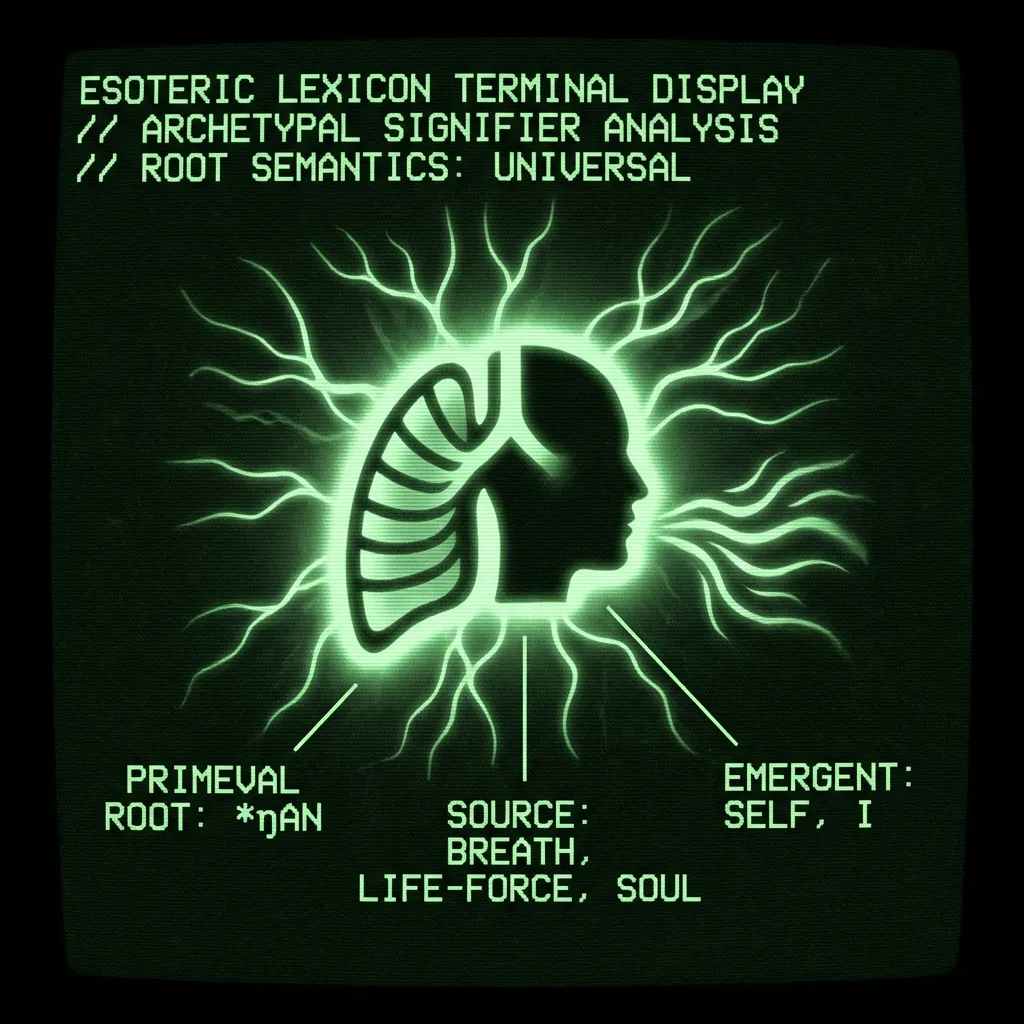TL;DR
- *ŋAN仮説は、「息、生命力、魂」を意味する超古代の原サピエンスの根を提案しています。
- 規則的な音変化(*ŋ > g/k/h/∅)を通じて、その子孫はPIE *an-(アニマ)、シノ・チベタン *ŋa(「私」)、オーストロネシア語 *qanitu(霊)などの言葉に世界中で見られます。
- 「息」から「魂」、「自己」、さらには「私」への意味の進化は、言語間で一般的な道筋です。
- この推測的な再構築は、音意味的パターンと文化的アーキタイプを統合することで、深い時間の言語学に対する批判に対処します。
- 証明されていないものの、この仮説は、息と人間性のつながりをエンコードする共通の言語化石の魅力的なモデルを提供します。
生命の古代の息:原サピエンス *ŋANの再構築
序論:自己となった息#
世界中の人間の言語は、「息」や「空気」を意味する言葉がしばしば「霊」や「魂」、あるいは生命そのものを意味する言葉としても使われるという興味深いパターンを共有しています。この観察は、超古代の原サピエンスの根*ŋANが元々「息、生命力、または魂」を意味し、何千年もの意味の漂流と規則的な音韻変化を経て、その子孫が世界中の言語で「霊」、「魂」、「人」、さらには一人称代名詞「私」を意味するようになったという大胆な仮説の基礎となっています。本報告では、*ŋAN仮説を詳細に提示します。提案された音韻経路(例えば、初期の軟口蓋鼻音*ŋがどのようにしてg、k、h、または消失するか)を概説し、「息」から「魂」、「自己」への意味の進化を追跡し、多様な言語ファミリーからの証拠を調査します。トーンは必然的に推測的です—原世界の再構築は伝統的な比較方法の時間の地平線をはるかに超えていますが、この仮説を興味深いものにする類型的、音意味的、文化的データを集めることにおいて権威を持つことを目指しています。また、偶然の収束や大きな時間深度での規則的な音法則の限界などの方法論的な課題と批判に対処しながら、*ŋANが息と人間性のリンクをエンコードする本物の古代の語彙的遺物である可能性があるというケースを構築します。
**ŋANの音韻経路とその世界的な反射#
この仮説の重要な柱の一つは、根*ŋANが異なる系統で規則的な音変化を経て、an、ŋa、gan、kan、han、hun、jin、khwanなどの形を生み出したということです。まず、初期子音*ŋ(軟口蓋鼻音)がさまざまな言語ファミリーでどのように進化するかを調べ、次に例を挙げて説明します:
*ŋの保持または喪失:* 多くの言語は、単語の始まりに*ŋを許可していないため、その喪失または修正につながります。したがって、*ŋANはしばしばan-(鼻音が落ちた状態)として生き残るか、補償的な声門の開始音を伴います。例えば、**原インド・ヨーロッパ語(PIE)**では、初期のŋは再構築できません。PIEの根は***h₂an-**または*an-(初期の鼻音なし)として現れ、「息をする」という意味です。この根はラテン語のanima「息、魂」とanimus「心、精神」、ギリシャ語のánemos「風」、古アイルランド語の*anál/anadl「息」、ゴート語のuz-anan「息を吐く」、さらには古アイルランド語のanimm「魂」を生み出しました—これらのケースでは、PIEの*an-は仮説の*ŋANに対応し、ŋが落ちた(または失われた喉頭音*h₂として反映された可能性があります)。
***ŋ > ŋ(保存):一部の言語ファミリーは初期の*ŋを保存しました。特に、原シノ・チベタン語は一人称代名詞*ŋa「私」として再構築されています。古代中国のテキストは「私」を吾や我のような文字で書き、古代中国語では*ŋˤaや*ŋˤajʔと再構築されています。多くの現代のシニティック言語はこれの痕跡を保持しています:例えば、広東語のngo「私」(*ŋoから)、上海語のŋu「私」。チベット語でもང(nga)を「私」として使用し、古代の*ŋを直接反映しています。これらのシノ・チベタンの例では、*ŋAN > ŋa(「私」を意味する)であり、これは*ŋAN「魂、自己」と意味的に関連していると主張します(意味の変化については後述)。同様に、オーストロネシア語ファミリーでは、原ミクロネシア語の再構築には「魂、霊」を意味する*ŋaanuや*ŋunuが含まれています(ミクロネシアのモートロック語のŋéén「幽霊、霊」とプルワト語のŋúún「魂」と比較)。これらは*ŋがプロト言語に保持され、後に一部の子孫で変化したことを示しています。
***ŋ > gまたはk(非鼻音化):多くの言語は初期の鼻音を破裂音に変えました。これはしばしば*ŋに起こり、g(有声軟口蓋破裂音)またはk(無声)を生じます。例えば、一部のチベット・ビルマ語では、一人称の形がk-とŋ-の形で現れ、接頭辞や方言の非鼻音化によるものと思われます。チベット・ビルマ語のキランティ支族では、リンブ語ではaŋaが「私」を意味しますが、関連するヤムプ語ではkaが「私」を意味し、元々の*ŋaが一部の系統で*ga/*kaになったことを示唆しています。同様に、初期のインド・ヨーロッパ語の方言が硬いG/K音を再導入した可能性があります:トカラ語Bの一人称単数代名詞āke(おそらく*ŋa-kaから)とシノ・チベタンの*ŋaを比較してください。推測的ですが、これらのヒントは*ŋANがgan/kanとして現れる可能性を示しています。実際、いくつかの研究者が提案する非常に初期の世界共通語の一人称は*anakuまたは*ŋakuであり、*a(n)-要素と-kuが含まれています。もし*ana-が「魂/自己」の根であったなら、*-ku(「私の」)を追加することで「私の魂」として「私」を表現する方法になる可能性があります。(注目すべきは、アッカド語の「私」を意味する言葉がanākuであり、原セム語*ʔanāku > アラビア語anā、ヘブライ語ani「私」となり、学者たちは長い間*an-要素を含むと解析しています。)この分析は、ŋAN > an(魂)が決定詞(-kuまたは類似のもの)と組み合わさって「私」形を生成し、後に融合した可能性を示唆しています。いずれにせよ、*ŋ > g/kが起こったのは、鼻音が失われたが調音位置が軟口蓋に留まったときであり、gまたは硬いc/kを生じた可能性があります。ラテン語のgenius(柔らかいg [dʒ]で発音される)という言葉にその微かな反響を見ることができるかもしれません。Geniusは実際にはPIE*genə-「生む、産む」から来ており、*ane-からではないため、別の根ですが、概念的な重なり—geniusが個人や場所の守護霊として—は、ラテン語でg-nの連続が個人の霊を意味するようになったことを示しています。民間伝承でのgenii/genieも霊であることは魅力的です。(英語の「genie」はフランス語のgénie < ラテン語のgeniusから来ており、アラビア語のjinnを翻訳するために使われました—形と意味の収束が見られます。)
***ŋ > h(摩擦化)または**∅:もう一つの一般的な経路は、特に声門要素が前にある場合、*ŋが声門摩擦音hに変わることです。いくつかの言語系統では、初期の軟口蓋鼻音が鼻音化された声門音または呼吸音として再解釈され、最終的にhとして聞こえるか、完全に失われることがあります。例えば、古代中国語の魂 *(hún)「魂」はm.qʷˤənまたはɢʷənとして再構築されており、ここでは根が鼻音の色合いを持つ([m.]接頭辞)uvular stop **q/**ɢを持ち、中期中国語では*h-開始音(MC hwon)になりました。したがって、古代中国語の*ŋʷənは*xwən > hwn > hunに変わった可能性があります。実際、中国語の魂 hún「霊的な魂」は、タイ語の「魂」を意味するプロトタイ語の言葉に非常に似ています:タイ語のขวัญ**(khwan、有気音kh)は「アニミズムの生命の本質;霊」を意味します。プロトタイ語はこの用語を*xwənAとして再構築しており、これは古代中国語の*qʷənと本質的に同じ音です(小さな接頭辞要素を無視すれば)。多くの学者はこれが偶然ではないと信じています:一方の言語が他方から借用したか、または共通の源からこの用語を継承したかのいずれかです。いずれにせよ、軟口蓋→声門のシフトが起こりました:中国語*ɢw- > h-、タイ語*ŋw-(または*qw-)> *xw- > kh-。*ŋAN仮説はこれを*ŋANの予測可能な変換と見ています:鼻音[ŋ]が無声摩擦音[h/x](弱化の一形態)になり、これらの言葉では母音*Aが*ɔまたは*uに低下した可能性があります(*xwənが*əまたは*unを持つ)。同様に、オーストロネシア語の同根語はqaNiCu > anitu/hantuを示しています:プロト・マライ・ポリネシア語qanitu(「祖先の霊、幽霊」)は、鼻音子音*N(オーストロネシア語の表記ではしばしば*ŋを表す)とともに、初期の*q(声門閉鎖音)を持っていました。多くの娘言語では、*qが落ちるか*hになり、*Nがnになりました:例えば、タガログ語のanito「霊、幽霊」(qa-niCuから、q-を失う)、マレー語のhantu「幽霊」(qa-nituから、q > hおよびnitu >ntu)。ポリネシアの同根語aitu/atua(霊、神)も同様にqanituから来ています(声門が失われ、*nが保持される)。これらは*ŋ/*q > ∅またはhのパターンを示しています。インド・ヨーロッパ圏でも類似の例があります:英語の「soul」は無関係(ゲルマン語*saiwalōから)ですが、「ghost」という言葉はPIE g̑hēis-「息をする」から来ています—異なる根ですが、注目すべきは息を伴うgh音で始まったことです。そして興味深いことに、エジプト語のankh(Ꜥnḫと書かれる)は、「生命、魂」を意味する古代の言葉で、声門子音(Ꜥ)とその後のnḫで始まり、「anh」のように聞こえます。エジプト語のꜤnḫが*ŋANと遠くから関連している可能性はあるのでしょうか?確かには言えませんが、象形文字で生命を描写する言葉(「☥」)が*an-音を含んでいるのは驚くべきことです。
***ŋ > 口蓋音またはy(口蓋化):あまり一般的ではありませんが、特定の環境下で軟口蓋鼻音が口蓋音にシフトすることがあります(特に前舌母音の前で)。いくつかの言語では、*ŋ > *ɲ(口蓋鼻音)> *y/j(接近音)に変わることがあります。もし*ŋANが*ŋɛnまたは類似の変種を持っていた場合、j-またはdz-音に至る可能性があります。これは推測的ですが、jin-タイプの形を考える一つの方法を提供します。例えば、ペルシャ語のjān(جان)は「生命、魂、精神」を意味し、しばしば「親愛なる」または文字通り「私の生命」という意味で使われますが、中期ペルシャ語gyān、古代ペルシャ語jiiyān-、最終的にはプロト・イラン語*gʷyān-(「息、生命」)から派生しています。プロト・イラン語*gʷyān-は、同じインド・ヨーロッパの根*an-「息をする」にリンクしており、明確でない起源の接頭辞*gʷ-を持っています。言い換えれば、ペルシャ語のjan「魂」は*an-のインド・ヨーロッパの反射(*g/*jが追加された)であり、プロト・サピエンスの借用ではありませんが、その音(jan~djan)は*ŋANパターンに適合します。*ŋ > g > jを許容する場合。次にアラビア語のjinn(جن)を考えてみましょう—アラビアの伝説の超自然的存在です。アラビア語のjinn(/dʒ/音)は「隠す/隠蔽する」を意味するセム語の根*√JNNから来ており(ジンは「見えない者」)、“息"とは無関係です。しかし、仮説のパターンとの類似性は興味深いです:jinnはjinのように聞こえます。これは純粋な偶然かもしれませんが、以前の基盤や収束が関与している可能性を問うのは魅力的です。いくつかの長距離比較言語学者は、セム語のʔan(ā)–「私」(ヘブライ語ani、アラビア語anā)とjinn「霊」が*an/*inパターンを反響していると指摘しています。ここでは注意が必要です:形式的な言語学はアラビア語のjinnを*ŋANから派生させません。それでも、音意味的な視点から、文化が霊の概念に似た音に引き寄せられる可能性があります—ある種の音象徴または単なる収束かもしれません。*jin-*を含めるのは、主に類似の形の世界的な星座を完成させるためであり、それが収束であり、同根ではない可能性があることを注意してください。
これらの音韻経路を要約すると、表1は**Proto-*ŋAN**がさまざまな形でどのように現れるかの概要を提供します:
*表1. ŋANの音韻反射のさまざまな言語ファミリーにおける例
| 反射パターン | 例の言語 | 形 | 音韻の発展 |
|---|---|---|---|
| an- (Ø-初期) | ラテン語、ギリシャ語、ケルト語(PIE反射) | anima(ラテン語「魂」)、anemos(ギリシャ語「風」)、anadl(古アイルランド語「息」) | 初期のŋの喪失(または*ŋ > h₂ > Ø);母音aが保存される |
| ŋa-(鼻音が保持される) | 原シノ・チベタン語、チベット語、広東語、ミクロネシア語 | ŋa(PST「私」)、nga(チベット語「私」)、ŋo(広東語「私」)、ŋéén(モートロック語「霊」) | ŋが[ŋ]として保存される。母音Aはしばしば/a/として保存されるか、一部では/e/に前進する(モートロック語)。 |
| ga- / ka-(軟口蓋破裂音) | キランティ(ヤムプ、ワリング)、おそらく初期IE方言 | ka(ヤムプ「私」)、aŋ-ka(ワリング「私」);(ラテン語genius「個人の霊」、本文参照) | ŋが[g]に非鼻音化されるか、[k]に無声化される;時には化石化した*k-接頭辞(いくつかのキランティ形で) |
| ha- / Ø-(有気音または喪失) | 中国語、タイ語、オーストロネシア語、セム語? | hun(古代中国語xwən「魂」)、khwan(タイ語「魂」)、hantu(マレー語「幽霊」)、anito(タガログ語「霊」)、(ヘブライ語/アラビア語のani/ana「私」) | ŋ > [h](中国語、マレー語)または> Ø(タガログ語、プロト・オーストロネシア語の*q/*ʔを落とす)。しばしば鼻音の代わりに声門閉鎖音や呼吸が置き換えられる。 |
| ja- / ɟa-(口蓋音/破擦音) | ペルシャ語、イラン語、(アラビア語) | jan(ペルシャ語「魂、生命」)、jān(アヴェスタ語「生命」);(jinn(アラビア語「霊」)は音の類似性のため) | ŋ > gʲ > [ɟ] > [dʒ]/[ʒ](口蓋化によりj音を生じる)。しばしば後続の口蓋滑音または高前舌母音(ŋA > ŋya)を伴う。 |
注: 上記の発展は一枚岩の音法則ではなく、さまざまなファミリーで観察された可能性のある傾向です。例えば、ŋ > gは一部のチベット・ビルマ語で起こり、ŋ > hは中国語とマレー語で見られます。各ファミリーの規則的な音法則は実証される必要があります—表は複雑な絵を単純化して世界的なパターンを強調しています。
*息から魂へ、そして自己へ:意味の漂流とŋAN意味フィールド#
もし*ŋANが「息、生命力」として始まったなら、どのようにして「魂」、「霊」、「人」、または「私」を意味するようになったのでしょうか?提案された意味の進化は、ほぼ普遍的なアニミズムのメタファーに基づいています:息は生命です。息が止まることは死を意味します;逆に、多くの文化は、身体に宿る霊を一種の空気や風として考えます。したがって、「息」から「霊/魂」への飛躍は、独立して多くの伝統で起こります。この意味の変化の証拠は豊富に見つかります:
インド・ヨーロッパ文化では、そのリンクは明示的です。ラテン語のanimusとanimaは元々「息」や「空気」を意味し、拡張して「霊、魂、生命の原理」を意味しました。ギリシャ語のpneúma(「息」)も同様に「霊」や神の霊を意味するようになり、ギリシャ語のpsychēは「息」を意味した後に「魂」を意味しました。古アイルランド語のanál「息」はanimm「魂」と同根です。スラブ語では異なる根ですが、古教会スラブ語のduchŭ(「霊」)はduchъ(「息」、cf.「息をする」dýchati)から来ています。これらはすべてインド・ヨーロッパ内の別々の語源ですが、一貫したメタファーのマッピングを示しています:息 → 生命 → 魂。PIEの根*ane-「息をする」自体がその反射の多様性にこのマッピングを示しています:例えば、サンスクリット語のánilaは「風」を意味し(世界の物理的な息)、サンスクリット語のātmanは異なる根*ēt-men-(「息をする」)から来ており、ウパニシャッド哲学の伝統で「魂、自己」を意味するようになりました。注目すべきは、ātmanが文字通り「息」や「霊」を意味し、ヴェーダ哲学で内なる自己や魂を指すために使われたことであり、まさに*ŋANに提案するシフトと並行しています。
シノ・チベタンおよび東アジアの文脈では、息と生命もリンクしています。中国の概念である氣 qì(古代* khiəp*、現代qì)は「空気、蒸気」を意味し、拡張して「生命エネルギー」を意味します。qìは異なる根ですが、中国語の魂 魂と魄 魄は二重の魂を表し—前者はより陽/霊的で、後者はより身体的であり、招魂(zhāo-hún「魂を呼び戻す」)は、苦しむ人のさまよう息魂を呼び戻す儀式です。魂という用語は、古代中国語のm.qʷənから来ており、タイ/タイ語のkhwanと一致し、どちらも身体を離れることができる一種の生命魂を意味します。タイの民間信仰では、個人の生命力であるkhwanが「失われる」ことがあり、健康を確保するために儀式的に呼び戻される必要があります。khwanと魂が音と意味を共有していることは、深く根付いた概念が(または古くに借用された)可能性を示唆しており、まさに*ŋAN仮説が予測するものです。一方、多くのチベット・ビルマ語は「息」や「風」を「霊」を意味するために使用します。例えば、一部のチベットの伝統では、rlung(風)が生命エネルギーとして使用され、ビルマ語ではleik-pya(文字通り「風」)が民話で霊や魂を意味することがあります。これらの類似点は、空気から魂への意味の飛躍が再発するパターンであることを強化しています。プロト-*ŋANの言葉は、文字通り息を意味し、自然に人の中の目に見えない活力の存在を意味するようになるでしょう。
「魂/霊」から**「人」や「人間」への拡張も理解できます。もし*ŋANが誰かの中の生命の霊や生命力を意味したなら、それは容易に人自体を表すためにシネクドキ的に使われる可能性があります—特に人が本質的に霊である文化では。英語ではその痕跡を見ることができます:「霊」という言葉は幽霊(身体を持たない人)を意味することができますが、古い用法では「霊」が生きている人を意味することもありました(「祭りで見た素晴らしい霊たち」)。多くの言語では、「人」や「部族」を意味する言葉が「息」や「生命」を意味する言葉から派生しています。例えば、仮説的な古ノルド語の用語ándi「息、霊」(アイスランド語のandiと同根)は、民族名Æsir**(神々)に関連している可能性があります—これは推測的ですが、「Asu」(霊/生命力を意味するヴェーダ語)をAesirに関連付け、「霊たち」を意味する可能性があります。その特定のリンクが成立するかどうかにかかわらず、一般的な考え方は、一群の人々が自分たちを「生きている者」または「霊的な者」と呼ぶかもしれないということです。驚くべきことに、プロト・オーストロネシア語の*qaNiCu(anitu)*は「死者の霊」を意味するだけでなく、**「祖先」や「古い者」**を意味する同根語を持ち、霊と人の境界を曖昧にしています。いくつかのオセアニア社会では、anito/hanituは祖先の幽霊と尊敬される長老の両方を指していました。遠い過去に*ŋANが同様に無形の魂と、拡張して生命を持つ祖先や人を指していた可能性があります。
最後の意味の飛躍は「人」や「自己」から代名詞へのものです。どのようにして魂/人を意味する言葉が「私」を意味する言葉になるのでしょうか?言語の進化で証明されている可能性のある経路があります。代名詞はしばしば強調された自己指定子(self、person、servant、childなど、文化に応じて)から由来します。例えば、タイ語の一人称代名詞ข้า(khâ)は元々「召使い/奴隷」を意味し(謙虚に「私」を表現するために使用)、日本語の男性のore(俺)は文字通り「自分自身」または「自分の側にいる者」を意味しました。もし*ŋANが「魂/自己」を意味する古代の名詞であったなら、それは「私自身」や「ここにいるこの人」を意味するフレーズで使われた可能性があります。何万年もの間に、そのような使用法が真の代名詞に文法化される可能性があります。比較言語学にはその証拠があります。セム語では、一人称独立代名詞ʔanāku(アッカド語、原セム語)は、指示詞や名詞基ʔan-から派生したと考えられることがあります。一つの推測的な分解はʔanā-ku =「これ(は)私」または「自己 + 私の(接尾辞)」であり、*an/*ŋanが自己/魂を意味したという以前の考えと一致します。同様に、ドラヴィダ語の一人称単数nāṉ(タミル語)、ñān(マラヤーラム語)、nānu(カンナダ語)はna-要素を含む可能性があり、自己を意味する(ただし、一部はドラヴィダ語*yan-/*nan-を別々に再構築します)。注目すべきは、完全に異なるファミリーの言語が-nまたは鼻音要素を持つ一人称代名詞を持っていることです:例えば、チベット語nga、中国語方言nga(「私」のため)、ビルマ語nga、タイ語の口語chan(おそらく古いca-ŋanから)、ドラヴィダ語nan/ñan、エジプト語の後期ink/ank(コプト語anok「私」として—anで始まる)、など。これはすべて偶然ではありえません;多くの言語学者は、代名詞の音パターンの限られた選択肢といくつかの偶然に帰しています(m-/n-代名詞のような統計的に一般的なパターンがあります)。しかし、*ŋAN仮説はより深い原因を示唆しています:これらの多様な「n」と「ŋ」の一人称形は、*ŋan/*anが「人/自己」を意味した超重要な時代に遡る可能性があります。実際的には、初期の人間が自分自身を意味するために「この魂」と言い、胸を指差していたかもしれません—そしてそのフレーズが「私」を意味する言葉として固定されたのです。実際、ある研究者は、ANAKU(原セム語「私」)が文字通り*「私の魂」*を意味した可能性があるという魅力的な例を挙げており、*an(u)*の所有形が代名詞を生む可能性を示しています。時間が経つにつれて、言語がより抽象的になると、元の意味「息」は代名詞の使用で忘れ去られ、霊的な語彙にのみ残りました。
以下の表2は、*ŋAN根に関連する主要な意味の変化を例とともにスケッチしています:
*表2. さまざまな伝統におけるŋAN(「息、生命」)からの意味の変化**
| 段階/意味 | 説明 | 反射の例 |
|---|---|---|
| 1.「息、一吹きの空気」 | 文字通りの呼吸や風、生命を示す行為 | PIE ane-「息をする」(サンスクリット語an-のániti「彼は息をする」);ラテン語animare「息/生命を与える」;ギリシャ語anemos「風」;ヨルバ語mí「息をする」(そこからẹ̀míが派生)。 |
| 2.「生命力、活力」 | 生き続けるための活力や生命エネルギー | ラテン語anima「息、生命、魂」;サンスクリット語prāṇa「生命の息」(*anからではなく類似);中国語氣 qì「息;生命エネルギー」;ヨルバ語ẹ̀mí「息、生命、魂」。多くの文化は息を生命そのものと考えます。 |
| 3.「魂、霊(目に見えない自己)」 | 人の無形の本質、しばしば眠りや死の際に身体を離れると信じられている | 古アイルランド語anim(m)「魂」;ラテン語animus「魂、精神」;古教会スラブ語duchu「霊」(「息」から);中国語魂 hún「魂」;タイ語khwan「霊、生命の本質」;タガログ語anito「祖先の霊」;マレー語hantu「幽霊」;モートロック語(ミクロネシア)ŋéén「幽霊、霊」;ヨルバ語ẹ̀mí「魂、霊」。また、アラビア語rūḥ「霊」は「風/息」から、ヘブライ語ruach「霊、風」。これらすべてが息=魂を示しています。 |
| 4.「人、人間」 | 活気に満ちた存在として見られる生きた人;時にはグループや部族の一員(「人々」) | プロト・オーストロネシア語qaNiCuは生きている長老にも適用されました(幽霊だけでなく);エジプト語ankh「生命」は「生きている人」を意味するように拡張されました(例:ni-ankh「生きている者」);おそらくPIE ansu-「霊」> アヴェスタ語ahu「主」(拡張)。より具体的には、中国語人(人、person)はOC niŋであり、これは異なる根ですが、形が*ŋanに驚くほど近いです;タイ語khon「人」(プロト・タイŋon、おそらく*ŋanから?)とその可能性のある同根語ラオ語konは、以前の鼻音*ŋを示唆しています。ŋan ~ ŋonが失われたアジアの基盤で「人間」を意味した可能性があります。英語では、「soul」が個人を意味することがあります(「50の魂が亡くなった」)。 |
| 5.「自己、アイデンティティ(再帰的)」 | 自分自身の概念、しばしば内面的な人間性や精神の感覚 | サンスクリット語ātman「自己、魂」(「息」から);ドイツ語Atmen「呼吸」対Atem「息、精神」は哲学的なdas Selbstを与えました;マレー語nyawa「魂、生命」はいくつかのイディオムで「自己」にも使われます。私たちは、プロト・サピエンスにおいて*ŋANがこのスロットを埋め、個人の本質を指していた(したがって*「自己」*)と仮定しています。 |
| 6. “I” (first person reference) | 話者のための代名詞としての自己概念の文法化。しばしば「人」や「この者」や「召使い」などを意味する言葉から発展する。| 原始シナ・チベット語 ŋa「私」(おそらく名詞「自己」から);原始セム語 ʔanāku「私」(ʔan- 要素を含む、おそらく「人」);ドラヴィダ語 ñān/nāṉ「私」;エジプト語 *ink/anok「私」(an-で始まる);英語の古語「soul」が反射的に使用される(「my soul is vexed」=「I am upset」)。ヨルバ語 emi「私」(強調代名詞)は文字通り ẹ̀mí「魂」を意味し、「自己」を意味するために使用される。ヨルバ語は明確なケースを提供する:emi は breath/spirit を意味し、それによって「私、自己」を意味する言葉となる。このように、現代の言語で呼吸から代名詞への連鎖が見られる。|
表2と例が示すように、「呼吸」から「私」への旅は長いが追跡可能である。呼吸という物理的な行為から始まり、*ŋAN は呼吸が伝える生命エネルギーの用語となる。次に、それは魂や精神、すなわち目に見えない活力を意味するようになる。そこから、それは人の本質や全体としての人(特に死体と対比して、または「多くの魂が洪水を生き延びた」のような文脈で)を指すことができる。反射的または強調的な方法で使用されるとき(「この魂はここにある」)、それは「自己」を言う方法となり、最終的に代名詞に文法化される。各ステップには強力な言語間の類似があり、単一の原始的な根が異なる系統でこの意味の変化を自然に経ることができるという考えに信憑性を与える。
この連続性の神話的および文化的共鳴も注目に値する。多くの創造神話には、神が呼吸を通じて人間に命を与えるというものがある。聖書の創世記では、神が「アダムの鼻に命の息を吹き込み、人は生きた魂となった」(創世記2:7)。シュメール神話では、女神ニンリルが彼女の息で枯れた植物を蘇らせる。命は呼吸であるという概念は非常に基本的であり、初期の人間の言語がそれらを結びつける言葉を持っていなかったとしたら驚くべきことである。もし *ŋAN がその言葉であったなら、その保存が世界の言語の多様性において—どれほど薄れていても—驚くべきことではない。広大な海と千年にわたって分かれた文化においても、類似の考えが見られる:例えば、ポリネシア人の間では、ha、命の息(「アロハ」のような挨拶に体現される)がある。ヘブライ語では、néshamah は呼吸と魂を意味し、ハッティ語(古代アナトリアの言語)では、pšun は「呼吸」と「魂」の両方を意味すると報告されている。このような類似は並行進化の結果かもしれないが、原始世界の種のための肥沃な土壌を提供する。
類型的、音象徴的、文化的相関#
生の言語学的証拠を超えて、*ŋAN 仮説を支持するためにさまざまな類型的および文化的データを集めることができる:
世界的な代名詞パターン: 特定の音が世界中の代名詞で偶然以上に繰り返されることが長い間指摘されている。よく知られた統計的傾向の一つは、ユーラシアにおけるいわゆる**「ママ/トゥ」または M-T パターン**(一人称 m、二人称 t)であり、アメリカの一部ではN-M パターン(一人称 n/ŋ、二人称 m)である。これらは統計的なものであり絶対的ではないが、代名詞音の深い時間安定性を示唆している。遠く離れた家族間でのn/ŋ の一人称の再発は、古代の *ŋa/*na の一人称の言葉の痕跡として解釈される可能性がある。例えば、北アメリカのペヌティアンおよびホーカン家族の言語はしばしば「私」に n を持ち、グリーンバーグとルーレンはこれを深い N-M マクロファミリー(「アメリンド」)の証拠と見なした。これらのマクロファミリーが有効かどうかにかかわらず、パターン自体は実在し、説明を求めている。*ŋAN 仮説は一つの説明を提供する:おそらく最初の話者(世界的な分散の前)は「私/私」に *ŋan のような言葉を使用し、それが後に置き換えられない限り、多くの娘系統に残った。すべての家族がそれを保持しているわけではない(インド・ヨーロッパ語族は名詞の「私」では保持していない)が、インド・ヨーロッパ語族でも斜格形では保持している:PIE 対格 *(e)mé >「私」(m-形)だが、PIE には特定の enclitics に生き残った強調一人称 *ana または *ono があったと主張する者もいる。これは推測的だが、無関係な言語を見たとき—ヨルバ語 emi、タミル語 naan、ケチュア語 ñuqa、ナワトル語 nehuā、アイヌ語 ani、シュメール語 ĝe(en)(おそらく「ĝene」私で)—「私」に鼻音の母音または子音がしばしば現れることは注目に値する。これは単に [n] が簡単な音であり、指示的マーカーになりやすいからかもしれない。しかし、音象徴的に、鼻音は話者の自己に関連付けられてきた(おそらくハムの音から、または鼻を通して空気を吹き込むことが自己感覚的な行為であるため)。ベングトソン&ルーレン(1994)のような深い比較分析者は、**“I” のための世界的な語源を ʔANA または MI として含めている—興味深いことに、ANA は ŋ を除いた我々の根である(彼らは ŋ を見逃したかもしれない)。この代名詞類型と我々の提案する根の収束は重要な類型的ポイントである。
音象徴と音の象徴性: *ŋAN 仮説は、特定の音が言語を超えて特定の意味と本質的に関連付けられている可能性から少し強化される。鼻音+開音節のシーケンスが自然に自己または魂と関連付けられる可能性があるか?「音象徴」の研究者の中には、鼻音が内向きの、自己指向の意味を伝えることができると主張する者もいる(例えば、m、n はしばしば「母」または一人称の言葉に現れるが、これは口が閉じているため、内向きの位置であるためかもしれない)。これは厳密な法則ではないが、m と n が me の言葉で非常に一般的であることは示唆的である。同様に、/a/ のような母音(低い中央の母音)は、多くの言語で「ここ/これ」を意味する指示詞でよく使用される—おそらくそれが非常に基本的で開かれた音であるため。ŋAN は鼻音 [ŋ]([n] に似た品質を持つ)と低い母音 [a] から成り立っている—音声的には、胸を叩くときに発する可能性のある原始的な音節として妥当である。初期の人間がこの単純な音節で自分自身やその重要な呼吸を指すことを想像するのは難しくない。さらに、[ŋ] は内面的と関連付けられることが多い音であり、一部の言語では準実用的に使用される(例えば、一部のバントゥー語では、nga が反射的接頭辞として使用される)。これは確固たる証拠ではないが、*ŋAN が自己/魂の言葉として「定着」した理由を説明する音象徴的な動機を提供する。
神話的原型: 文化的に、もし *ŋAN が魂または精神の古代の言葉であったなら、神話的な名前や宗教的概念にその反響が見られることが期待される。以下の魅力的な対応を考えてみよう:多くの神話では、最初の人間または最初の精神の名前は Anu/Anna/An のようなものである。シュメール神話には「An」(またはアッカド語で Anu)が天空の神として登場する—直接「呼吸」ではないが、天/空気の神として。神 An(u) が「空」から名付けられたのか「精神」から名付けられたのか?シュメール語の an(空)が呼吸/風の概念と結びつく可能性があると推測する者もいる(空は風と精神の領域である)。エジプト宗教では、ankh 記号(☥)は生命の鍵であり、その名前 ankh は「生命」であり、我々の根の反響を持つかもしれない。また、エジプトの神話では、「akh」—人の魂の一つ、輝くもの—が類似の音の根から来ている可能性がある。北欧のエッダでは、オーディンが最初の人間アスクとエンブラに与えた贈り物には önd(古ノルド語で「呼吸/精神」)が含まれていた。古ノルド語の önd(*and/*andan、「呼吸」から)は、我々の *an- 根とプロト・ゲルマン語 *andjan(ゴート語 us-anan 参照)を介して同根である。名前にもそれが見られる:名前 Andrew(ギリシャ語 Andreas)は anēr「人」(おそらく元々は「呼吸者」を意味した?それは PIE *h₂ner-、異なる根で「人」を意味するが、an- のように聞こえるのは興味深い)。ペルシャの叙事詩の英雄 Jamshid は Yima(Yama から)とも呼ばれ、アヴェスター語では yam「双子」に関連しており、我々の根とは関係ないが、Yima は長寿を与えることに関連しており、おそらく Jamshed「輝き」と呼ばれたが関係ない。それでも、世界中で、An-/On- で始まる名前が精神や生命と関連付けられることが繰り返される:Ani はエジプトの心の擬人化であり、Anna はキリスト教の神秘主義で恩寵と関連付けられる(おそらく単に「恩恵」)。これらの神話的なメモは証拠ではないが、ŋan/an のようなものが生命と精神の音の象徴として深い文化的意識に浮かんでいたことを示唆する。もしプロト・サピエンスのコミュニティがそのような言葉を持っていたなら、その共鳴が言語家族が分岐しても保存された理由かもしれない。
マクロファミリーにおける用語のクラスター: 深い比較言語学者は、マクロファミリーの根を提唱する際に関連する意味の星座を探すことがよくある。我々の場合、もし *ŋAN がプロト・ワールドの「魂/呼吸」であったなら、「呼吸する」、「鼻」(呼吸の器官)、または「生きる」を意味する関連形が期待されるかもしれない。実際、一部の仮説は an- を 鼻 の言葉に結びつけている(例えば、プロト・オーストロネシア語 anu「鼻」が提唱されているが、他の人は *idu を再構築している)。デネ・コーカシアンの提案(バスク語、コーカシア語、シナ・チベット語などを結びつける)では、「生きる」または「生きている」を意味する *HVN または *ʔAN のような根がある。例えば、バスク語には arnasa「呼吸」(arnas- が an から来ている可能性がある)があり、animu「魂、勇気」という言葉がある(おそらくロマンス語からの借用であるが、それでも興味深い)。一部のコーカシア語では、魂を意味する言葉は am(w)- または han- である。これらは偶然か借用かもしれないが、スプリッターからルンパーに転向した者にとって、それらはパターンを形成する。*ŋAN モデルは、以前は無関係と考えられていたより多くの反射を将来の研究が発見することを予測している。例えば、ナイル・サハラ語族では、ディンカ語の nyàn は「蛇の精神」を意味する(おそらく無関係だが、*ŋan -> nyan は考えられる)。アメリカでは、アルゴンキン語族にはマニトゥ(偉大な精神)がある—興味深いことに manitu/anitu に非常に近い(実際、学者たちは manitou < manitoo が独立して造られたと考えているが、manitu がクリー語で精神を意味し、anitu がタガログ語で精神を意味するのは面白い並行である)。これらのクロスコネクションは、呼吸 = 精神 = 自己 が遠く離れた言語で類似の音にエンコードされた言語の普遍性である可能性を強調している。
要するに、類型的パターン(鼻音の一人称代名詞のような)、音象徴的関連(自己のための鼻音 +「あ」)、および共通の文化的メタファー(命は呼吸である)はすべて、*ŋAN の提案された軌跡と一致している。これらのいずれも単独では単一の起源の決定的な証拠ではない—独立した革新は非常にあり得る。しかし、仮説の強さは証拠の収束にある:ユーラシア、アフリカ、オセアニア、アメリカの言語形式がすべて魂/自己のための鼻音母音の根を指し示し、その根に意味を与えるほぼ普遍的なメタファー。ある支持者が言ったように、もしそのような類似が一つか二つの地域でのみ発生したなら、それらは偶然かもしれないが、「しかし、同じ意味で、同じ子音群が数十の異なる言語群で見つかるなら、偶然について話すことは、空から隕石が落ちてきて、その飛行中に何度も金の指輪に形を変えることについて話すようなものだ。」 つまり、精神/人を意味する *ŋAN のような言葉の世界的な再発は、偶然の並行性よりも共通の祖先を示している可能性がある。
深い比較方法論と規則性の問題#
「プロト・サピエンス」根を提案することは、伝統的な歴史言語学の快適ゾーンを大きく超えることを必要とする。比較方法が厳密に適用されると、プロト言語を約6,000〜10,000年前(例:プロト・インド・ヨーロッパ語、プロト・アフロアジア語)まで自信を持って再構築できるが、プロト・ワールドは約50,000〜100,000年前—最初のホモ・サピエンスの言語コミュニティの時代—に存在するだろう。このような広大な時間のスパンでは、規則的な音の対応を追跡することが非常に難しくなる。あらゆる世界的な語源(*ŋAN を含む)に対する主要な批判は、言及された言語を結びつける確立された規則的な音法則の欠如である。実際、主流の言語学者は、体系的な音の対応がなければ、似たような言葉はほとんど意味がないと主張している—人間の言語には比較的少ない基本的な音声形があるため、いくつかの重複は偶然に期待される。 *ŋAN 仮説はこれに正面から向き合わなければならない:
収束対同根: 多くの言語が鼻音の音とハミング(呼吸)または擬音(おそらく呼吸のハミングを模倣する)との自然なつながりのために「魂」に似た音を独立して選んだ可能性はあるか?これは可能である。擬音と象徴的な音が類似の言葉をもたらすことが知られている(例えば、mama は母親のために世界的に使用されている)。しかし、呼吸はかなり静かな音である—柔らかい息は、例えば、咳やアチューのような擬音ではない。もし何かが擬音であるなら、huh のような喘ぐ音が模倣されるかもしれないが、ŋan は明らかな擬音ではない。*ŋAN のような用語の分布の広さと意味の特定の結びつきは、純粋な収束よりも可能性が低い。例えば、mama/papa の場合よりも。*ŋAN 仮説を支持する者は、1つか2つの類似が偶然である可能性があるが、同じ根がすべての大陸で同じ概念のために見られるとき、偶然の仮説は大いに緊張することを指摘している。統計的には、比較に独立性がある限り、より多くのグループを比較に加えると、ランダムな収束の確率は指数関数的に減少する。我々の表には、インド・ヨーロッパ語族、アフロアジア語族、シナ・チベット語族、オーストロネシア語族、ニジェール・コンゴ語族(ヨルバ語)、おそらく他の言語がすべて *an ~ ŋan を精神/私のために示している。すべてが偶然に一致する確率(意味の一致を伴う)はおそらく小さい。しかし、批評家は、何千もの言語と限られた音素があるため、いくつかの重複が世界的に発生するだろうと反論している—そして我々はパターンを見つける者として、我々の物語に合うものを選んでいるかもしれない。これは有効な注意である。我々は *ŋAN を支持するデータを選択し、反例を無視していないことを確認しなければならない(例えば、多くの言語には魂や私のための全く異なる言葉があり、類似性がない)。
規則的な音の対応の欠如: たとえ *ŋAN の言葉が広範に存在しても、音が規則的な法則を通じて一致しないという批判がある。インド・ヨーロッパ語の anima とシナ・チベット語の ŋa とオーストロネシア語の anitu とセム語の anā —はい、すべて *an または *na を持っているが、懐疑的な人にとってこれはあまりにも緩い。実際の遺伝的関係では、体系的な対応が期待される(例えば、プロト・ノストラティックの提案は PIE *n = アフロアジア語 *n = ドラヴィダ語 *ṇ などを規則的に整列させようとする)。我々の仮説は、失われた多くの中間段階を超えている;我々は既知のプロトファミリーを除いて、プロト・サピエンスから現代の言語に飛躍している。これは古典的な証拠を求める者にとっては弱点である。*ŋAN 仮説は、現在のところ、100k年前から今日までの変化の整然とした規則的な連鎖を示すことができない。代わりに、それは多くの言語の形-意味のペアリングの大量比較に依存している。ジョセフ・グリーンバーグが開拓したアプローチである。グリーンバーグの多国間比較は、最初に厳密な音法則を避け、代わりに世界的なパターンを探し、次に対応パターンを見つけようとする。ライル・キャンベルやドナルド・リンゲのような批評家は、規則的な音の対応がないと、偶然の類似によって無関係な言語を誤ってグループ化する可能性があると主張している—悪名高い*「ピザの偶然」*(イタリア語で pizza が「パイ」を意味し、フィンランド語で piirakka が「パイ」を意味するのは偶然であり、関係の証拠ではない)。*ŋAN は大規模なピザの偶然か?バランスを取るために、我々は多くの主流の言語学者が、規則的な音法則がないためにプロト・ワールドの語源に納得していないことを認識している。例えば、インド・ヨーロッパ語の p はセム語の f に体系的に対応する可能性があるが、IE *n- と中国語 *h- の体系的な関係は何か(anima と hun のように)?一見すると、何もない—しかし、それはこれらの家族が非常に長い間分岐しているため、中間段階(したがって中間の規則的なシフト)が失われているためである。支持者は、すべての中間プロト言語があれば、段階的に変化を説明できると主張している(実際、プロト・東アジア語が魂のために *ŋ- を持ち、中国語が *h- に変えたと想像することができる;プロト・ノストラティックが呼吸のために *ħan を持ち、それが IE で *an に、アフロアジア語で *ʔan に、など)。しかし、それらの再構築は仮説的である。この仮説は、規則的な音の変化の基準が緩和されるレベルで動作することになる。これは論争の的であるが、完全に方法がないわけではない:研究者は言語をより高次の家族(例:ノストラティック、デネ・コーカシアン、オーストリック)にグループ化し、まずそれらのマクロファミリー内で比較方法を適用しようとする。*ŋAN がこれらのマクロファミリーのいくつかで示されることができれば、それはそれがそれらに先行していたことを強化する。例えば、*an はインド・ヨーロッパ語とアフロアジア語(ノストラティック?)にあり、*ŋa はシナ・チベット語とナ・デネ(デネ・コーカシアン?)にあり、*an はオーストロネシア語とオーストロアジア語(オーストリック?)にあり—各マクロファミリーが同根セットを生み出すなら、推移的に *ŋAN はプロト・ワールドにあったかもしれない。批評家は、それらのマクロファミリー自体が未証明であるため、それは少し循環論法であると反論している。
時間の深さと侵食: 最高の意志を持ってしても、~300世代の言語(~1,000年ごとの言語変化の世代を仮定)を超えて単一の言葉を再構築することは非常に野心的である。音の変化、意味の変化、借用、置換が水を濁すだろう。多くの言語学者は、安全な再構築はおそらく~10,000年を超えることはできないと信じている。なぜなら、最終的にはすべての音声パターンが混乱するからである。しかし、特定の超保存された言葉や根がはるかに長く生き残る可能性があるという反対の見解もある。例えば、「指/一」を意味する tik や「水」を意味する akwa のような言葉が多くの家族で世界的に現れると主張する者もいる(ルーレンは27の世界的な語源をリストアップした)。もしそれらの主張が何らかの水を持つなら、*ŋAN「呼吸」は別の超保存された言葉かもしれない—おそらく「水」や「石」よりも初期の人間にとってさらに重要であったかもしれない。なぜなら、生きている存在(呼吸者)を識別し、その中の生命を概念化することが基本的であった可能性があるからである。また、*ŋAN が各系統で連続して生き残ったのではなく、接触を通じて再作成または保存された可能性もある。例えば、ある古代のグループが *ŋAN を持ち、別のグループが魂のために異なる言葉を持っていたが、文化的交流(結婚、儀式の共有)を通じて一つの用語が広まった場合、それは用語が家族の境界を越えた方法を説明するかもしれない。初期のモダンヒューマンとともに広まった古代のワンダーワード(放浪語)のアイデアはクレイジーではない—例えば、boom(音のために)は言語を超えて類似している、または一部の初期の道具名が広まったかもしれない。もし *ŋAN が初期の精神的または宗教的な語彙の一部であったなら、移住する部族がそれを互いに借用し、それによって多くの系統に種をまいた可能性がある。これは遺伝的な絵を複雑にする(それはまっすぐな継承ではないが、それでも人間の使用において非常に古い言葉である)。
反例と否定的証拠: 仮説を真にテストするには、それが当てはまらない言語を見なければならない。呼吸/精神/私を意味する言葉が完全に無関係な形を持つ主要な家族はあるか?はい、たくさんある:例えば、テュルク語の魂の言葉は tın(古代テュルク語 tın「呼吸、魂」が現代トルコ語の can を与えた、興味深いことにテュルク語で jan と発音される—これは我々のパターンに一致する!)。日本語では tamashii(魂)と watashi(私)があり、*an のようなものはない。ドラヴィダ語の「魂」は明確に *an ではない(タミル語では「生命」を意味する uyir が魂に使用され、無関係)。バントゥー語では -moyi または -pɛpɛ が呼吸を意味する(例:リンガラ語 mɔ́í「魂」、スワヒリ語 roho はアラビア語から)—*an ではないが、興味深いことに一部には mu-ntu「人」があり、-ntu は *-tu(*an ではない)からの根かもしれない。*ŋAN が多くの場所で失われたり置き換えられたりした可能性があるが、それはそのような時間に期待される。しかし、例えば、オーストロネシア語が魂のために独立した言葉を持っていた場合(*qaQaR のようなもので、*n がない)、それは主張を弱める。オーストロネシア語には kalag(ビサヤ語 kalag「魂」)などの他の魂の言葉もあるため、qanitu は複数の用語の一つに過ぎなかった。世界的な絵は混乱しているため、我々が適合するケースに焦点を当て、それに合わないケースを無視していると主張することができる。厳密なアプローチは統計的テストを必要とする:「呼吸/生命/魂/私」を意味する言葉が、世界の言語全体でランダムなチャンスよりも N-A-N のような音を持つ頻度が高いか?もしそうなら、それは遺伝的または機能的な原因を示すかもしれない。もしそうでないなら、我々はノイズの中でパターンを見ているかもしれない。
これらの課題と批判を認識するのは、仮説を弱めるためではなく、それが非常に野心的であり、まだ言語学者によって広く受け入れられていないことを明確にするためである。*プロト・ワールド仮説は主流の外にあり、すべての言語に共通の起源を証明するのに十分な証拠を持つことができるかどうかを疑う専門家が多い。*ŋAN 根はこの推測的な事業の中で提案されている。そのため、それに対する議論は累積的で学際的であり、厳密に言語学的ではない。我々は文化的普遍性と広範な類型に依存しており、古典的な歴史言語学者が説得力がないと感じる方法で依存している。例えば、多くの文化で呼吸 = 生命であることを指摘することは興味深いが、それがそれらの言葉が共通の祖先を持つことを証明するわけではない—それは単に並行メタファーである可能性がある。我々はしたがって、あまりにも多くを主張することに注意しなければならない。*ŋAN 仮説は、共通の起源を示す可能性があるが、確かにより多くの研究と証拠(特に中間の再構築と代替説明の考慮)が必要な、クロスカルチャーの言語的事実のセットを一貫した方法で整理するモデルまたは物語として見られるべきである。
批判とより強力なモデル#
*ŋAN モデルのバランスの取れた、しかし好意的な絵を描くために、主要な批判と我々の応答を要約しよう:
- 批判1:「小さな音節の偶然の類似性。」 批判者は、*ŋAN は非常に一般的な音を持つ CVC 音節であると指摘している。ほぼすべての言語には /n/ または /ŋ/ と /a/ 母音がある。何千もの概念と限られた音素があるため、無関係な言葉が一致することは避けられない。応答: 我々は an ~ na が独立して容易に生じる可能性があることを認める。しかし、意味の特異性が我々のサンプル全体で注目に値する。我々は「魚」や「星」のような任意の言葉を比較しているのではない—我々は一貫して重要な呼吸、魂、または自己の言葉を見ている。ランダムであれば、類似の形の意味の特定のクラスタリングが家族全体で見られることは期待されない。呼吸/生命と魂/人が鼻音+母音の基盤を持つことが非常に多いという事実は、純粋な偶然から離れる可能性を傾ける(特に各大陸で複数の独立した例があることを考慮すると)。さらに、一部の形(ŋ を持つもの、または派生形で *nt や *nd のような特定のクラスターを持つもの)は、単に「na」よりも音声的に些細ではない。プロト・マラヨ・ポリネシア語 *qanitu は特定の形を持ち、プロト・シナ・チベット語 *ŋa も同様である。それらの整合性は偶然では完全には説明できない。したがって、偶然を排除することはできないが、データの全範囲に対する説明としては不十分であるように思われる。
批判2:「規則的な音法則がなく、ただの緩い比較 – 疑似科学だ!」 伝統主義者は、音法則なしの大量比較は厳密ではないと主張します。仮説の根拠を選り好みすることで、どんな仮説的な根でも「証拠」を見つけることができると。実際、以前の「グローバル語源学」の試みはまさにその理由で批判されました。 応答: 私たちは、私たちの証拠が、例えばラテン語の p がギリシャ語の ph、サンスクリットの p に対応するような印欧祖語 *p- のような性質のものではないことを認めます。それは異なるスケールの比較です。しかし、利用可能な場合には規則的な音変化の洞察を取り入れようとしました。例えば、原タイ語 *xwən と古代中国語 *qʷən がよく一致し、中国-タイ接触または共通の祖先の既知のパターンに適合することを指摘しました。また、シノ・チベット語族内では、*ŋa → *a または *ka というパターンが文書化されています。印欧語族内では、*h₂enh₁ -> *an や時には *ne(否定や代名詞で)ということが知られています。したがって、問題をより小さなマクロファミリーのチャンクに分割すれば、それぞれに比較法を適用できます。例えば、原クラ・ダイ語で *ŋVn を再構築し、古代中国語で *ŋʷən を再構築し、それらが約4000年前の共通の祖先から来た可能性があるかどうかを確認します。ローラン・サガールトのような学者は、タイ語の *khwan と中国語の *hun が共通の起源を持つオーストロ・タイの接続を実際に提唱しています。それは規則的な音法則のシナリオです(中国語 *m-qʷən 対 タイ語 *xwən)。同様に、ノストラティック研究では、「呼吸する」に対する *an- が比較されています。イリッチ=スヴィティッチはノストラティック *ʔănćV(「息/精神」)を再構築し、それがアフロアジア語族 *nafš-(ヘブライ語 nefesh「魂、息」など)と印欧語 *ans-(仮説的だが、実際には印欧語には *ane- がある)を生むとしています。したがって、私たちは小さな対応を試み、それを集約しようとしています。最終的な集約(プロト・ワールド)は通常の範囲を超えているため、パターンに頼らざるを得ません。また、規則性はより深いレベルでまだ存在する可能性があることを強調します。たとえば、*ŋAN が *ʔAN や *HAN のようなバリエーションを持ち、異なる結果をもたらした可能性があります。もし一貫した規則(例えば、プロト・ワールドの初期の ŋ がアフロアジア語族で声門閉鎖音になり、シノ・チベット語族で *h になり、印欧語族でゼロになる)が見つかれば、それはケースを強化します。現在、それらの対応は仮説的ですが、あり得ないことではありません。例えば、声門閉鎖音と *h は多くの子孫言語でのプロト・アフロアジア語族の喉音の反射です(エジプト語の Ꜥnḫ は Ꜥ で始まり、プロト・アフロアジア語族の声門閉鎖音 *ʔan(a)ḫ が「生きる」であった可能性があります)。そして、PIE *h₂(喉音)はそれ自体が以前の ŋ または ʕ を反映しているかもしれません。大胆なノストラティック主義者は、PIE *h₂en「呼吸する」がアフロアジア語族の *ʕan(咽頭音)から来ていると提案しています – したがって、プロト・ワールドの *ŋ/ʕ への潜在的な規則的リンクです。これは推測的ですが、あり得ないことではありません。要するに、完全に作業された音法則マトリックスが欠けている一方で、規則性を完全に無視しているわけではありません。むしろ、系統を超えて原始音素が整列している(例えば、開始時の鼻音または喉音、/a/ 母音)ことが見られ、それが体系的な対応への第一歩です。
批判3:「時間の深さが大きすぎる – 言語はそれほど遠くまで再構築を許さない。」 多くの言語学者、おそらく大多数は、8000〜10000年後には語彙の証拠が再構築に信頼できるほどには残っていないと信じています。100,000年後には、基本的にすべての語彙が置き換えられるか、認識できないほどに変形されると主張されています。 応答: この保守的な見解は、最近のいくつかの研究によって挑戦されています。これらの研究は、超安定的な単語の小さなコアを示唆しています。例えば、Pagel et al.(2013)は、他の単語よりも変化が遅い単語(代名詞、数詞、親族用語を含む)を発見し、10,000年以上にわたって家族を超えて保持される可能性があるとしています。特に代名詞は粘着性があることが知られています(例えば、英語の「I」はPIE *eg(h)om から直接来ており、約6000年以上生き残っています)。「I」や「魂」がいくつかの系統で20,000年続くことは考えられないことではありません。もし複数の系統が後に出会う(例えば、アフリカからの脱出を通じて)なら、彼らは古代の保持を共有するかもしれません。また、100,000年前の人間は完全に現代的な認知能力を持ち、言語において似たような基本的なニーズを持っていた可能性が高いと考えています – 家族、身体部位、自然環境、生命や死のような存在的な概念のための単語です。もし何らかの単語が保存されていたとしたら、それらかもしれません。火や水の単語はしばしば革新されるかもしれませんが、息の単語は – タブーや置き換えが少ないため – 持続したかもしれません。確かに、100,000年は長い時間です。しかし、例えとして、いくつかの遺伝子や神話はそれほど遠くまで遡ることがあります。なぜ単語がそうでないのでしょうか?ホクレアの議論(太平洋を横断する星による航海)は、口承文化でさえ驚くほど古い知識を保存できることを示しています(ポリネシア人は50世代にわたって口承の歴史を運びました)。言語は動的であり、すべてを保存するわけではありませんが、特定の根本的な形態素(特に新しい文法に再付着できる短いもの)は生き残るかもしれません。*ŋAN は赤ちゃん言葉、儀式の詠唱、または神々の名前で持続したかもしれません、たとえ日常の言語がその周りで変化しても。要するに、極端な時間の深さを障壁ではなく、学際的な証拠を必要とする挑戦として扱っています(したがって、文化や神話のデータを使用しています)。それは従来の限界を超える仮説です – それは完全に認めます – しかし、それは少なくとも人間の文化的連続性と一致する方法で構築されています(例えば、魂の概念はおそらく人類と同じくらい古いので、そのための単語もそうかもしれません)。
これらの批判に対処する中で、私たちは *ŋAN 仮説をより強力なモデルに洗練させます。それは単に「見て、これらの単語は似ている」というものではなく、中間レベルでの規則的な変化を統合し、この特定の根が保存される理由を説明し(その基本的な意味とおそらく音象徴のため)、新しいデータが出現するにつれて修正に対してオープンであるものです。私たちは効果的に *ŋAN を意味のコアのための作業再構築として提案しています。歴史言語学、遺伝人類学、認知科学のさらなる研究が支持証拠を発見するかもしれません – または説明できない反例を見つけてそれを否定するかもしれません。どちらの結果も、言語が最も基本的な人間の経験をどのように符号化するかについての理解を深めるでしょう。
結論: 言語の化石としての生命の息#
私たちは仮説的な深い過去の単一音節 – *ŋAN – から現在の広大な言葉とアイデアのネットワークへと旅をしてきました。コア仮説は、*ŋAN が単なる単語ではなく、単語に符号化されたアイデアであったということです:息は生命であり、生命は精神であり、精神は人格の本質であるというアイデアです。規則的な音韻変化(鼻音が破裂音になったり消えたり、母音が変化したり)と意味の自然な拡張(「息」から「魂」へ、「自己」へという比喩と換喩)を通じて、この原始的な記号は世界中の言語に識別可能な痕跡を残していると主張しています。私たちは印欧語族(an- に anima、anil- など)、シノ・チベット語族(ŋa「私」、中国語 hun)、オーストロネシア語族(qanitu > anitu/hantu)、アフロアジア語族(おそらくエジプト語 ankh、セム語 anā「私」)、ニジェール・コンゴ語族(ヨルバ語 emi)などで *ŋAN の可能性のある反射を特定しました。音変化と意味変化の表を構築し、必然的に単純化されているものの、各ステップの妥当な経路を示しています。また、方法論的な論争についても議論し、すべての言語学者がこれらの接続を証明されたものとして受け入れるわけではないことを認めています。
重要なのは、なぜこの特定の根がそれほど特別であるかを示そうとしたことです。それは人間の自己認識の中心に位置しています(呼吸は生命の最初と最後の兆候です。自分自身を呼吸する存在として知ることは意識の出現において重要であったかもしれません)。私たちが「私は」と言うとき、私たちの遠い祖先が彼らの内なる本質について最初に話したときの息を無意識に反響しているかもしれないと考えることは詩的です。推測的であるとはいえ、*ŋAN 仮説は説得力のある物語を提供します:旧石器時代の暗闇で、ある男が寒い夜に息を吐き、口から出る見えない霧が「彼」であることに気づいたときに発せられた単一の音節が、今日まで私たちの言語に共鳴し続けているということです。それは呼吸という身体的行為と自己の無形の感覚との連続性を符号化しています – それは世界中の初期の神話作家やシャーマンが理解し、伝えた連続性です。
この仮説を提示する中で、私たちはモデルの「強い」バージョンを描きました – それは実際の遺伝的(共通の起源)関係を前提としています。その強いバージョンが証明されないままであっても、この試みは有益です。それは、言語の起源の理論が説明しなければならない世界の言語のパターンを強調します:なぜ多くの言語が息と魂を結びつけるのか?なぜ多くの一人称代名詞が鼻音で始まるのか?なぜ anima、anito、ani (I)、nga (I)、hún、khwan、jan のような単語が少数の音に集まるのか?均一主義的な見方(似たような人間の経験の下での独立した発展)はその一部を説明できます。単一起源の見方(単一の起源)は別の部分を説明できます。現実は混合かもしれません:おそらく祖先の単語 *ŋAN が存在し、一部の言語がそれを保持し、他の言語が後にそれを再発明したのは、概念がその音を要求したからです。私たちの仮説はそれらの見方を統合しようとする試みであり、その概念が非常に顕著であったため、元のラベルがしつこく残り、失われたときでさえ、新しい言語が類推によって似た音の単語を再発明する傾向があったことを示唆しています。
*ŋAN 仮説の究極のテストは将来の研究にあります:より多くの古代DNAが移動の手がかりを与え、より多くの原始言語が再構築され比較されると、パターンは保持され、中間形態を通じて説明可能でしょうか?例えば、プロト・ノストラティックが「魂/息」のために *ʔăn(V) を持ち、プロト・オーストリックが *qanay を持ち、両方が共通の *ŋan から来たことを発見することを想像します。または、2つの遠く離れたインスタンスを結びつける古代の碑文や借用語を発見することを想像します(例えば、ネオリシックの儀式の詠唱が保存され、アジアとアフリカの両方で「精神」のための *ngan のような単語を使用しているシナリオを想像します)。これらは夢ですが、不可能ではありません。
推測的な枠組みとしても、*Proto-Sapiens *ŋAN 仮説は重要な機能を果たします:それは、世界の言語の喧騒の背後に、私たちの祖先が遺伝子や道具だけでなく、言葉 – 彼らの存在の最も深遠な要素のための言葉を共有していた時代のかすかなエコーがあるかもしれないことを思い出させます。「息、精神、生命、自己」 – これらは確かに思考する人間の最初の関心事の一つでした。単一の声のジェスチャー、*ŋAN がこれらの概念をすべてカプセル化し、さまざまな形で今日まで話され続けていると考えることは満足のいくことです。広東語の話者が「私」を意味する ngo(我)と言い、ヨルバ語の話者が「私」または「精神」を意味する emi(ẹmi)と言い、タイの母親が赤ちゃんの khwan について話し、古いロシアの民話が zhivat’(生きている)魂について語るとき、彼らは知らず知らずのうちに、かつて**「内なる生きた息」を意味した**ウル単語の断片を繰り返しているのかもしれません。
結論として、プロト・サピエンス *ŋAN 仮説は未だ証明されていないものの、歴史言語学、意味論、人類学からの証拠を一貫した物語に結びつける説得力のあるモデルです:*ŋAN が生命の息のための古代の単語であり、規則的な音変化(ŋ > g/k/h/∅)と意味の拡大(息 → 魂 → 人 → 代名詞)を通じて、その遺産が精神と自己のための言葉の世界的な星座に見られるということです。それは壮大で冒険的な仮説であり、興奮と健全な懐疑を招くものです。私たちが示したように、それを支持する強力なパターンと類似性がありますが、対処すべき論理的な批判もあります。音韻対応をさらに洗練し、文書化されていない言語でより多くの「化石」単語を探すことで、この仮説をさらにテストできます。そして、最終的な結論に関わらず、*ŋAN を探求することは、言語、思考、文化がどれほど密接に織り交ぜられているかを深く理解することにつながります – 私たちが最初に息を吸う時から最初の言葉を発する時まで、そしておそらく、私たちの種が集団で最初に発した言葉に至るまで。
出典: 証拠と例は、印欧語の語源学的資料、シノ・チベット語の再構築、オーストロネシア語の比較データ、魂の概念に関する民族言語学的研究を含む広範な言語学研究の調査から引き出されています。これらは提案された根の広範な反射とそれに付随する文化的概念の両方を示しています。深い再構築と偶然の収束に関する批評家の視点も注目され、議論が既知の言語学原則に基づいてバランスが取れたものとなるようにしています。この仮説は進行中の作業であり、さらなる探求への招待であり、完成した証明ではありませんが、単なる偶然以上のものかもしれない魅力的な言語の一致の基盤に立っています。
出典#
- Ruhlen, Merritt (1994). On the Origin of Languages: Studies in Linguistic Taxonomy. Stanford University Press.
- Bengtson, John D. & Ruhlen, Merritt (1994). “Global Etymologies.” In On the Origin of Languages.
- Pagel, Mark, et al. (2013). “Ultraconserved words point to deep language ancestry across Eurasia.” PNAS 110(21): 8471-8476.
- Watkins, Calvert (2000). The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. Houghton Mifflin.
- Baxter, William H. & Sagart, Laurent (2014). Old Chinese: A New Reconstruction. Oxford University Press.
- Blust, Robert & Trussel, Stephen (2010). Austronesian Comparative Dictionary. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
- Campbell, Lyle (2013). Historical Linguistics: An Introduction. MIT Press. [For a critique of deep reconstruction]
- Dixon, R.M.W. (1997). The Rise and Fall of Languages. Cambridge University Press. [For discussion on time depth limitations]
FAQ#
*Q1. ŋAN 仮説とは何ですか?
A. これは、古代のプロト・サピエンスの単語 *ŋAN が「息」または「魂」を意味し、世界の言語ファミリー全体で精神と自己に関連する類似の音の単語の祖先であるとする推測的な言語理論です。
Q2. 単語が15,000年以上生き残ることができるのはどうしてですか?
A. この仮説は、特に「魂」や「私」のような基本的な概念のための「超保存」単語が置き換えに抵抗し、言語変化の千年を通じて生き残ることができると示唆しています。
Q3. この理論の主な証拠は何ですか?
A. 証拠は、無関係な言語ファミリー(例:PIE *an-、シノ・チベット語 *ŋa、オーストロネシア語 *qanitu)での類似の音の単語の「星座」であり、すべてが息、精神、または自己に関連しており、偶然ではなく共通の起源を示唆しています。
Q4. なぜこの仮説は主流の言語学で受け入れられていないのですか?
A. 主流の歴史言語学は、非常に広範な時間の深さを超えて確立するのが非常に難しい規則的な音対応に依存しています。この理論は非常に推測的であり、伝統的な比較法の範囲外と見なされています。