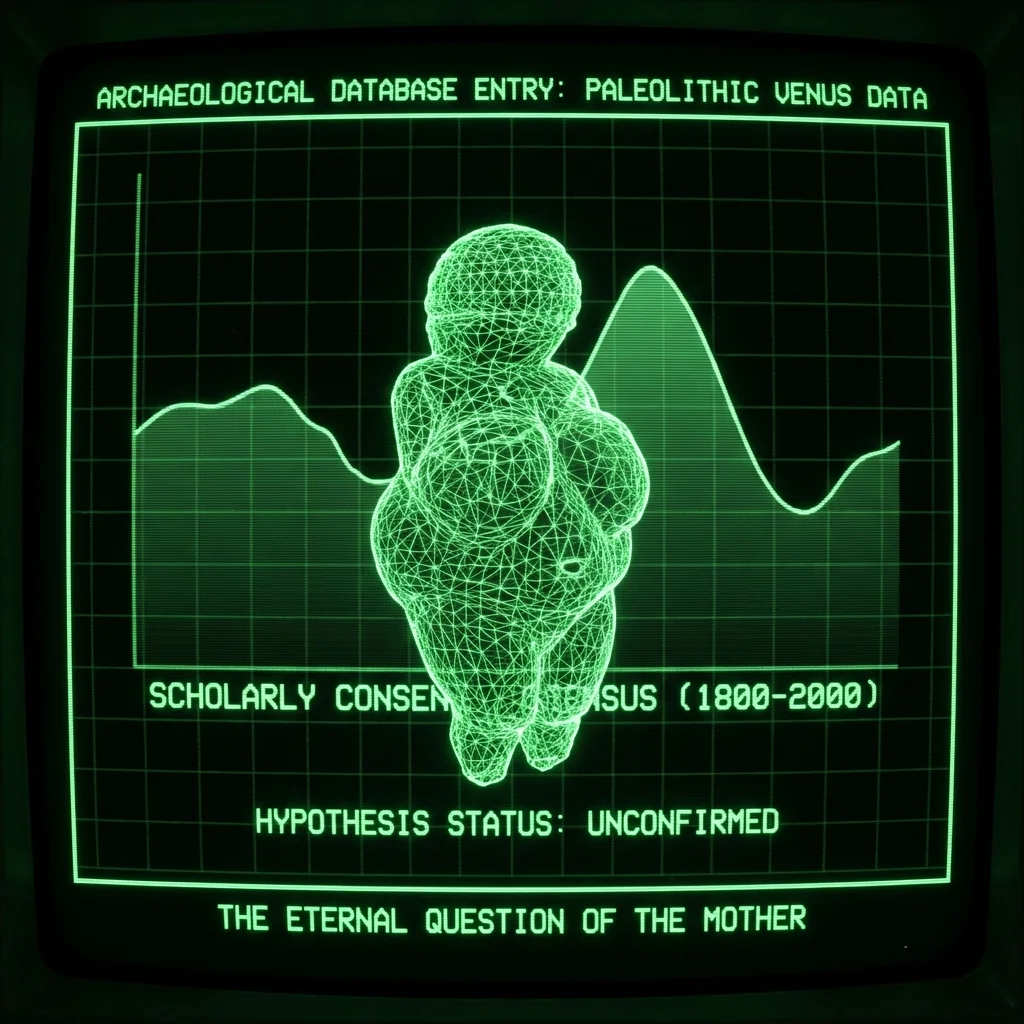TL;DR
- 世界の神話はしばしば女性の創造者を描き、古代の母権制(女性の支配または中心性)の理論を刺激している。
- J.J.バッホーフェン(1861年)は、普遍的な「母権」段階を提案し、エンゲルス、フェミニスト、さらには一部のナチス思想家にも影響を与えたが、しばしば神話の解釈に基づいている。
- 19世紀から20世紀の人類学者はこれを議論し、モーガンのような人物は支持したが、メイン、ウェスターマルク、後のマリノフスキーは批判し、女性の政治的支配の明確な証拠を見つけられなかった。
- 第二波フェミニズムは関心を復活させた(例:ギンブタスの「古代ヨーロッパ」)が、証拠の欠如と代替解釈を強調する学術的批判に直面した(例:バンバーガーの神話は父権制を正当化する)。
- 現代の研究は、文字通りの母権制ではなく、女性の具体的な貢献(祖母仮説、協力的育児、母語による言語起源、革新/農業における潜在的役割)と霊長類の類似(ボノボ)に焦点を当てている。コンセンサス:証明された母権社会はないが、女性は文化形成において重要な役割を果たした。
神話と宇宙論における女性創造者#
世界の神話において、女性はしばしば原初の創造者や文化の伝達者として登場する。オーストラリアのアボリジニのドリームタイムの物語では、例えば、祖先の姉妹たちが法と儀式を確立したとされる。アーネムランドのワウィラク姉妹は、最初の人々に「多くの法と儀式を定め」、今日まで続く道徳規範を教えた。彼女たちが旅をする中で、土地に名前を付け、神聖な儀式を創造し、ヨルングの伝統における文化の重要な要素を実質的に築いた。類似のテーマは他の場所でも見られる:ナバホの宇宙論では、チェンジング・ウーマンが中心的な人物であり、双子の文化英雄を産み、「地表の人々」の世界を形作り、秩序と新しい存在を創造に導入する。日本の神道の伝説では、太陽の女神アマテラスは生命を与える太陽の力を体現するだけでなく、神話的には皇族の祖先であり、初代日本天皇は彼女の子孫とされ、社会的権威の神聖な女性起源を示している。
これらの神話は、女性を生命と法の創造者として描いている。多くの初期社会は地球や肥沃さを女性として擬人化した—古代ヨーロッパの偉大な母神から先住民の伝説における「最初の女性」まで。先史時代の芸術は同様の考えを示唆している:旧石器時代の「ヴィーナス」像の普及は、一部の学者に古代の母神の崇拝を仮定させ、初期の人類が文化と共同体の源として女性の創造的原理を崇拝したと示唆している。解釈はさまざまだが、このような神話的および象徴的な証拠は、女性がかつて社会で支配的な役割を果たし、最初の人間の制度を生み出したと想像する後の理論家たちの舞台を整えた。
バッホーフェンの母権制:母権制の先史時代#
文明の創始者としての女性に関する現代の学術的な考えは、ヨハン・ヤコブ・バッホーフェンの1861年の重要な著書『母権制』(Das Mutterrecht)に始まる。スイスの法学者で古典学者であるバッホーフェンは、人間社会が父権制以前の初期の女性支配の段階を経たと提案した。彼は、人類の原始時代には無秩序な関係(「ヘタイリズム」)が支配的であり、父性が不確実であったため、母親を通じてのみ血統と相続が追跡できたと主張した。バッホーフェンによれば、これにより、女性が唯一の確認可能な親であるため、高い名誉と権威を享受する普遍的な母権制(Mutterrecht)の時代が生まれたとされる。彼は「最初の人間社会は母権制であり、広範な無秩序が反映された女性神の崇拝が特徴であった」と信じていた。彼は神話を社会進化の化石記録のように扱い、神話は「人々の発展段階の生きた表現」であると主張した。例えば、彼はギリシャ悲劇のオレステスを、母権制が父権制に取って代わられる象徴として見ていた。(劇中で、新しい神々アポロとアテナがオレステスを支持し、父の系統が母の系統よりも重要であるという原則を正当化し、父権制の勝利を寓意的に表現している。)バッホーフェンはまた、外国の習慣の報告(例えば、アジア・マイナーのリュキア人の母系親族を指摘)や考古学的な女性のシンボルに基づいていた。これらすべてから、彼は文化的段階の壮大な進化的スキームを構築した:無秩序なヘタイリズムから、農業と女神崇拝に代表される母権制、地球と肥沃さに中心を置く時代が生まれ、それが最終的に父権制の秩序に取って代わられた。
特に、バッホーフェンは母権制の時代を平和と社会的調和の時代として理想化していた。彼の見解では、「人類史の母権制の時代は崇高な壮大さの時代」であり、女性の価値観が支配していた:母親は「純潔と詩」を鼓舞し、男性の「野蛮で無法な男らしさ」を抑えながら平和と正義を追求した。彼はこの女性的原理が家族と社会を神聖化し、より攻撃的な男性原理に取って代わられるまで続いたと信じていた。バッホーフェンの感情的で(もし推測的であれば)作品は、父権制への移行を深い革命として描写した。彼は例えば、ギリシャ神話では、新しい父権的な神々の到来が「母権制を打倒する奇跡を成し遂げる」ために必要だったと書いている。
バッホーフェンの理論は、その時代において大胆で異端的であった。彼の神話の直感的な読み取りと、伝説が先史時代の社会的現実の「現実的であれば歪んだ」絵を保存しているという主張は、より経験的な学者を動揺させた。著名なフィンランドの人類学者エドヴァルド・ウェスターマルクは、『人間の結婚の歴史』(1891年)でバッホーフェンの方法を拒否し、「神話や伝説が人々の『集団的記憶』を保存しているというバッホーフェンの考えに動揺した」。
それにもかかわらず、『母権制』は、世代を超えて多くの思想家に(良くも悪くも)大きな影響を与える種を植えた。ある歴史家が述べているように、バッホーフェンは「女性を中心にした人間と文化の発展の理論を創造した」とし、最初は無視されたが、彼の考えは後にドイツのイデオロギーのスペクトル全体で取り上げられた—社会主義者、ファシスト、フェミニスト、反フェミニストのいずれにも。
進化人類学と母権制論争(1860年代–1900年代)#
バッホーフェンの仮説は、人類の制度に対する進化的枠組みを構築していた時期に登場した。19世紀後半、多くの著名な学者が、社会の進化の普遍的な段階を探求しながら、古代の母権制の概念を支持または反対した。
一方で、バッホーフェンは、文化進化の普遍的な段階を探していた初期の人類学者や社会理論家の間で熱心な支持者を見つけた。アメリカの民族学者ルイス・ヘンリー・モーガンは、イロコイ族の研究で有名で、先史時代の社会が母系クランを中心に組織されていたと独自に結論付けた。『古代社会』(1877年)で、モーガンは多くの先住民族が母親を通じて親族関係を追跡し、原始人類が集団結婚を実践し、母親が唯一の確実な親であると提案した。彼は、ネイティブアメリカンの「分類的」親族システムに、初期には「女性系統による血統」が一夫一婦制と父系血統の台頭以前の標準であったという手がかりを見た。モーガンの証拠に基づくアプローチ(イロコイ族、ポリネシア人などからの民族誌データに基づく)は、バッホーフェンの直感にある程度の経験的な重みを与えた。彼は、父権的で一夫一婦制の家族が人類史において比較的遅い発展であり、彼が「母系クラン組織」と呼んだ長い時代に先行していたと確信した。
イギリスの人類学者ジョン・ファーガソン・マクレナンもまた、1865年と1886年に初期社会が母系血統を持っていたと主張し、「外婚制」という用語を作り、妻の捕獲と女性の不足が、間接的に以前の母権制システムを示唆する習慣を導いたと提案した。マクレナンは最終的に、母系血統を原初と認識したバッホーフェンを称賛した。『金枝篇』の著者として有名なジェームズ・G・フレイザーもまた、この考えに魅了され、バッホーフェンの主張を比較民俗学と神話で強化しようとした。
おそらく最も影響力があったのは、マルクス主義理論家フリードリヒ・エンゲルスであり、原始的な母権制の概念を歴史的唯物論に織り込んだ。『家族、私有財産および国家の起源』(1884年)で、エンゲルスはモーガン(彼は家族の「先史時代」を発見したとして称賛した)とバッホーフェンの洞察に大きく依存した。エンゲルスは、母権制の崩壊が私有財産の台頭と密接に関連していると主張した。彼は、部族の共産主義社会では、女性が比較的高い地位を持っていたが、富が蓄積され、相続のために父性が重要になると、男性が支配権を握ったと論じた。エンゲルスは有名な言葉で書いた:「母権制の打倒は女性の性の世界史的敗北であった…女性は貶められ、奴隷化され、…単なる子供を産む道具となった。」エンゲルスによれば、この「敗北」は、性別間の最初の階級的不平等をもたらし、それがその後の階級の階層化によってさらに悪化した。彼は父権制の出現を、相続財産と父性の確実性を確保するために設計された一夫一婦制の結婚の出現と結びつけた。
エンゲルスの劇的な表現は、左翼とフェミニストの間で母権制仮説を広く普及させた。また、原始的な母権制の信念を特定の政治的解釈にしっかりと結びつけた:マルクス主義者にとって、原始的な母権制は、階級社会の台頭によって覆された初期の共産的で平等な社会の形態を表していた。この政治化は時折、経験的証拠を覆い隠した。人類学者ロバート・ロウィは後に、エンゲルスや他の人々がモーガンとバッホーフェンのビジョンに魅了されすぎて、「母権制の時代の歴史的現実」がしばしば仮定されるだけで証明されていないと述べた。
一方、他の学者は原始的な母権制の概念に強く反対した。イギリスの法学者サー・ヘンリー・メインは、早くも1861年に、最初の社会の基本的な社会単位は母権的なクランではなく父権的な家族であると主張した。メインは古代法の背景を持ち(ローマのパトリア・ポテスタスの古典的なイメージに影響を受けて)、父親の権威と父系親族が原初的であると主張した。彼はバッホーフェンのような理論を、ローマ法の歴史や聖書に反する推測的な「ロマンス」と見なした。1891年、ウェスターマルクの結婚に関する広範な研究は、母系親族が多くの文化で一般的である一方で、女性が男性を支配する過去の時代の明確な証拠はないと結論付け、バッホーフェンの神話的証拠を否定した。20世紀の変わり目までに、多くの人類学者は、女性が男性を政治的に支配する真の母権制の社会が存在したことはないと懐疑的であり、その懐疑は民族誌データが増えるにつれてさらに強まった。
20世紀初頭の展開:女神崇拝から批判へ#
20世紀の幕開け頃、母権制仮説は新しい証拠によって洗練され、出現する社会科学者によって攻撃された。支持的な側面では、古典学者ジェーン・エレン・ハリソンとケンブリッジの儀式主義者は、バッホーフェンの考えを古代ギリシャ文化に適用した。ハリソンは、ヘレニズム以前のギリシャが女神中心の宗教とおそらく母系の社会習慣によって特徴付けられていたと信じていた。『ギリシャ宗教研究の序論』(1903年)や『テミス』(1912年)などの作品で、彼女は多くのオリンポスの神話や儀式(デメテルの崇拝、アマゾンの物語など)が、より古い母権制または少なくとも「母親中心」の時代の痕跡を保存していると主張した。彼女のギリシャの芸術と神話の解釈は、後の男性支配のパンテオンの下に感情的で共同体的な女性中心の基盤があると仮定した。ハリソンは、古代ギリシャの文化を「母権制」が後の侵略によって覆されたものとして描写し、バッホーフェンの進化的物語に一致させた。これはより保守的な古典学者からの反発を招いた:ルイス・ファーネルやポール・ショーリーのような学者は、しばしばその時代の性別バイアスに彩られた言葉でハリソンを鋭く批判した。彼らは彼女の母権制の考えを空想的とし、彼女の学術理論を「性の自由ヘレニズム」と呼び、女性の解放というスキャンダラスな概念に結びつけて非難した。このような反応は、議論が当時の態度と交差していたことを示している—ハリソンの作品は、女性参政権運動が盛んだった時期に、古典学の学問をフェミニストが転覆させたものとして効果的に攻撃された。
この時代における「文化の創始者としての女性」仮説の最も野心的な拡張は、ロバート・ブリフォールトの『母たち:感情と制度の起源の研究』(1927年)であった。フランス生まれのイギリス人類学者であるブリフォールトは、民族誌の例を百科事典的に集め、文明のほぼすべての基本的な側面が母性の領域から起こったと主張した。彼は、初期の人間の社会生活が女性の貢献によって形作られたと主張した:彼の見解では、家族自体が「女性の本能の産物」であり、女性が最初に社会的絆を創造した。ブリフォールトは、原始的な母権制を必ずしも女性が男性を政治的に支配するものとしてではなく、女性が社会的に中心で文化的に創造的であるものとして定義した。彼は例えば、最初の儀式や宗教的カルトが女性によって発展したと推測し、月の女神や月経タブーの広範な重要性を指摘し、女性が「月のカルトの最初の神秘家」として初期の精神的権威を持っていたと結論付けた。彼はまた「ブリフォールトの法則」を定式化し、その一般的な形では次のように述べている:「動物の家族のすべての条件を決定するのは女性であり、男性との関係から利益を得られない場合、そのような関係は成立しない。」つまり、持続可能な家族や社会単位は女性のニーズと選択に基づいて形成される。(ブリフォールトは動物について述べており、人間社会が動物のハーレムと同一であるとは言っていない。それにもかかわらず、人間の家族が母性のイニシアティブから生まれたという暗示があった—女性が有用な場合にのみ男性をグループに受け入れる。)
ブリフォールトの作品は、結婚や料理から法や宗教に至るまで、文明を女性が発明したと大胆に主張した。これは、狩猟や道具作りのような男性の活動が進歩を促進したという従来の物語に直接挑戦するものであった。しかし、当時の主流の人類学者は納得しなかった。1920年代後半までに、社会人類学は機能主義と単線的進化への懐疑に向かっていた。ブロニスワフ・マリノフスキーは、母系のトロブリアンド諸島民を研究し、ブリフォールトの結論に異議を唱えた。マリノフスキーは、父性の概念がない社会(トロブリアンド諸島民は子供が祖先の霊から受胎すると信じていた)でも、男性は無関係ではなく、母方の叔父や夫がグループの社会的および政治的生活で重要な役割を果たしていることを発見した。彼は1930年代にブリフォールトと議論し、初期の人間の家族はおそらく常に重要な男性の貢献を伴っていたと主張し、「母親中心」の段階が誇張されていると述べた。マリノフスキーの分析では、女性に排他的な権力を与える社会は知られておらず、変化するのは母親または父親を通じて血統が追跡されるかどうかであり、男性に対する女性の「支配」ではなかった。
さらに、一部の学者はより複雑な進化モデルを提供した。オーストリアの民族学者ヴィルヘルム・シュミットは1930年代に文化の多線的起源を提案した:彼は、さまざまな生態学的要因に応じて、母系、父系、父権的な3つの主要な先史文化タイプがあると示唆した。特に、シュミットは、初期の植物栽培における女性の役割が彼女たちの地位を高め、いくつかの地域で女神崇拝を促進した可能性があると主張した。これは、女性が農業を開始した可能性が高い(採集者として植物を家畜化した)という現代の理論や、織物や陶器のような重要な技術を発明し、新石器革命を促進したという理論に似ている。シュミットの作品は今日ではあまり引用されていないが、文化の起源に性別と環境の両方を組み込もうとする試みを示しており、単一の普遍的な母権制の時代を仮定するのではなく。
世紀半ばまでに、新しい民族誌の証拠の重みは、ほとんどの人類学者を母権制仮説に対する批判的な立場に導いた。部族社会の調査では、女性が支配する政治システムの明確な例は見つからなかった。人類学者アルフレッド・ラドクリフ=ブラウンは1924年に「母系クランは母権制ではない」と宣言した—すなわち、母系親族を女性が男性を支配することと混同してはならない。1930年、E.E.エヴァンズ=プリチャードは、古代の母権制の段階の概念全体が男性の幻想(または不安)の産物であり、歴史的現実ではないとさえ示唆した。それにもかかわらず、失われた女性主導の時代のアイデアは魅力的であり、すぐに異なるイデオロギーの文脈で新たな命を見出すことになる。
イデオロギーと解釈:原始的母権制の政治#
文化における女性の優位性の問題は、権力とアイデンティティの根本的な問題に関わるため、初めからイデオロギーと絡み合ってきた。母権制仮説に対する反応は、時代の精神を反映していることが多い—ビクトリア朝の父権制からナチス・ドイツ、第二波フェミニズムまで。
父権的な規範を支持するビクトリア朝の人類学者や社会理論家は、母権制モデルに最初に抵抗した人々の一部であった。前述のサー・ヘンリー・メインの父権制理論は、現状を守るための一部として見ることができる:それは聖書の族長の物語と一致し、男性の権威が自然で原初的であると仮定するビクトリア朝の社会規範と一致していた。バッホーフェンやモーガンの発見が広まると、一部の保守的な学者はそれを脅威と見なした。父性が遅れて発見され、初期社会が女性の系統を尊重していたという概念は、父親の神から与えられた役割についてのキリスト教とビクトリア朝の信念と衝突した。1900年代初頭のある参考書が辛辣に述べたように、発展段階としての母権制の概念は「科学的に持続不可能」であり、その用語自体が誤解を招くものである。このような否定は、その時点で学術的な確立が主にそのアイデアを拒否していたことを示している—おそらく経験的な理由だけでなく、深く根付いた父権的な物語に挑戦したためである。
ドイツ語圏では、バッホーフェンの作品は20世紀初頭に復活し、ナショナリストやファシストの思想家の間で意外な支持者を見つけた。これは驚くべき歴史的なねじれである:ナチスが公にアーリア人男性を称賛し、女性を「子供、台所、教会」に追いやった一方で、一部のナチス知識人は古代母権制の神話に興味を持っていた。学者たちは「母権制の神話」が奇妙な政治的両義性を持っていたことを指摘している:それは極左(マルクス主義者、フェミニスト)と極右に訴えることができた。1920年代と30年代のドイツでは、さまざまなフォルキッシュ(民族主義的民俗)作家がバッホーフェンを取り入れた。例えば、ナチスの著名な哲学者アルフレッド・バウムラーは、インド・ヨーロッパの過去に男性と女性の原理の相乗効果を見ていた;彼は原始的な女性支配の時代を認めたが、それを現代の性別秩序の高貴な対比として描いた。彼は(バッホーフェンのように)女性の独立がかつては現実であったが、男性のリーダーシップによって正当に克服されたと信じていた—しかし彼はまた、母権制の過去の精神的理想を復活させることが国を再生させることができると示唆した。もう一つの例は、ナチス党の主任イデオロジストであるアルフレッド・ローゼンベルクであり、『20世紀の神話』(1930年)で原始的な母権制に言及した:ローゼンベルクは失われたアーリア人の黄金時代を想像し、それは正確には母権制ではなかったが、古代「北欧」民族の間での女性と母の象徴の高い地位を強調した。ナチスの母権制理論の支持者は、女性が男性を支配するものとしてそれを枠組み化することは決してなかった;代わりに、彼らは「ドイツ的母性」を民族共同体(Volksgemeinschaft)の養育的な核として理想化した。実際には、彼らは古代の威信を利用して母性を賛美した—しかし、男性の戦士精神が依然として優勢である厳密にバランスの取れた性別秩序の中でのみ。
これらのアイデアに対するナチスの関心は、周辺的でやや矛盾していたことに注意することが重要である。第三帝国の全体的な立場は、父権制と男性の支配が自然であるというものであった(ヒトラーとヒムラーは女性の社会的優位性を信じていなかった)。しかし、ある学者が書いているように、「母権制に関するバッホーフェンの考えは、ナチスの指導者の中でも支持者を見つけた、アーリア人の男らしさを称賛する体制にもかかわらず」。このパラドックスは、母権制の物語がどれほど可変的であるかを示している:ナチスの手にかかると、それは反動的な理想を強化するためにねじ曲げられた—しかし、政治的には従属的な母親としての女性を理想化するために。第二次世界大戦の終わりまでに、しかし、そのような概念は公式の言説からほとんど消え、ナチスのオカルト主義とフォルキッシュの疑似歴史との関連によって汚された。
ソビエト連邦や他のマルクス主義の文脈では、母権制理論は異なる経歴を持っていた。エンゲルスの権威は、20世紀初頭に原始的な母権制(とその崩壊)のアイデアをある種のマルクス主義の正統性にした。ソビエトの人類学者や歴史家は、エンゲルスに従い、母権制を持つ原始共産主義、次に父権制を持つ階級社会、そして最終的に平等を回復する未来の共産主義という社会的段階の順序を教えた。実際には、1920年代から50年代のソビエトの研究は、ソ連内外の人々の間で母系クランの証拠を探し、モーガン=エンゲルスの枠組みに適合する発見を強調することが多かった。しかし、彼らはこれらのグループで女性が支配していたと主張することは避けた—それは女性の支配よりも共同体的な社会構造に関するものであった。この物語の政治的な有用性はマルクス主義者にとって明らかであった:それは現代の父権制(そして拡張的には資本主義)が永遠でも自然でもなく、歴史的な発展であり、覆すことができることを強調した。それでも、20世紀後半までには、エヴェリーナ・B・パヴロフスカヤのようなマルクス主義の学者でさえ、「古典的な母権制」は決して文書化された現実ではなかったことを認め始め、代わりに初期社会の相対的な平等性について話すようになった。
1970年代、第二波フェミニズム運動の中で、先史時代の女性中心の時代のアイデアが最も広く普及し、新たな学術的な精査を引き起こした。多くのフェミニスト作家、アーティスト、活動家は、記録された歴史に欠けている女性の自律性と尊敬を持つ古代の女神文化のビジョンに触発された。考古学的な発見と再解釈がこれを助長した。特に、リトアニア系アメリカ人考古学者マリヤ・ギンブタスは、「古代ヨーロッパ」という概念を進めた。これは彼女が女神崇拝、平等主義、母権的と特徴付けた新石器時代の文明(紀元前7000年から3000年のバルカン半島とアナトリア)である。ギンブタスの発掘調査は多数の女性像を明らかにし、彼女は母神宗教を示すシンボルを特定した。彼女の見解では、これらの古代ヨーロッパ社会は平和で女性中心であり、インド・ヨーロッパの遊牧民—父権的な戦士—が侵入し、男性支配の秩序を課すまで続いた。ギンブタスはこれらの文化を母権制と呼ぶことは避けた(彼女は「女性中心」や母権的といった用語を好んだ)、なぜなら彼女は女性が男性に対して公式な権力を持っていたと主張していなかったからである。それにもかかわらず、彼女の作品はフェミニストによって、父権制が常に規範であったわけではないという証拠として受け入れられた。
一方で、エリザベス・グールド・デイヴィス(『The First Sex』、1971年)やマーリン・ストーン(『When God Was a Woman』、1976年)といった著者による人気のある本は、失われた母系社会と女神宗教の黄金時代を鮮やかに描写しました。彼らは、バッホーフェン、ブリフォールト、ギンブタスといった資料(および想像力豊かな再構築)を基に、女性が農業、文字、医学を発明し、平和に統治する最初の文明化の力であったと主張しましたが、男性の暴力がそのバランスを崩したとしています。これらの作品はフェミニストの精神運動と共鳴し、20世紀後半に女神のスピリチュアリティとネオペイガンの実践の急増に貢献しました。ある人々にとって、「女性が神として崇拝された」遠い時代を信じ、男性支配のない社会を信じることは、父権制に対する神話的な対抗物語として非常に力強いものでした。あるフェミニストのサークルでは、この「母系社会の先史時代」はほぼ教義となり、代替の未来を想像するために使われました。歴史家シンシア・エラーは、「あるフェミニストのサークルでは、私が母系社会の先史時代の神話と呼んだものが政治的教義として君臨し、他のサークルでは思考の糧を提供し、さらに他のサークルでは新しい宗教の基盤として機能した」と述べています。
しかし、この熱狂的な復活は、願望的思考を懸念する多くのフェミニストを含む学者からの批判的な反応を引き起こしました。早くも1949年には、シモーヌ・ド・ボーヴォワールが母系ユートピアの考えに冷水を浴びせました。『第二の性』において、ボーヴォワールは、元々の母系社会の仮説を「バッホーフェンの空想」として退けました。彼女や他の20世紀中頃の知識人(フランスの人類学者フランソワーズ・エリティエなど)は、女性の神や母の象徴が一般的である一方で、女性が集団として先史時代に支配したという証拠はないと主張しました。1974年には、人類学者ジョーン・バンバーガーが「母系社会の神話:なぜ原始社会で男性が支配するのか」という有名なエッセイを発表し、女性がかつて権力を持っていたとされるアマゾンの部族の神話を検証しました。バンバーガーは、これらの物語が男性によって警告的な物語として語られ、女性が権力を持つとそれを誤用するため、現在男性が支配しなければならないことを正当化していることを発見しました。彼女の結論は、母系時代は男性によって作られた神話であり、女性の自律性に対する不安を反映しているというものでした。これは、女性の支配の神話が実際の過去の証拠ではなく、現在の社会的目的(しばしば「女性が支配する」混乱を示すことで父権制を強化するため)に役立つという以前の機能主義的解釈を反映しています。
20世紀後半までに、考古学者、人類学者、歴史家の間での学術的コンセンサスは、女性が一般的な規則として男性に対して政治的権威を行使する厳密な意味での母系社会が人類史上知られていないというものでした。多くの平等主義的または母系社会が存在しますが、それらは「女性が支配する」文化の鏡像ではありません。Wikigender百科事典が簡潔に述べているように、母系社会という用語自体が問題となり、ほとんどの学者はバッホーフェンの連続モデルを「科学的に持続不可能」と見なしました。先史時代の女性に関する理論の支持者であるギンブタスのような人々でさえ、女性の支配を意味するため、母系社会という言葉を避け、より微妙な用語(例:「母系中心」、「女性中心」など)を選びました。それにもかかわらず、学術界の外では、失われた母系社会のビジョンが一般の想像力とフェミニストの意識に入り込みました。それは、進化と歴史における女性の役割についての貴重な議論を引き起こしましたが、「母の時代」の具体的な証拠はありません。
証拠に焦点を当て直す:人類学、生物学、言語#
近年、いくつかの分野の研究者たちは、女性の人類の物語への貢献について、実証的な記録が何を教えてくれるかに議論を向け直しました。「母系社会は存在したのか?」という問いを立てるのではなく、女性個人や女性主導の活動が人類の進化や文化の発展にどのように重要だったのかを探求しています。このアプローチは、イデオロギーの極端から、より証拠に基づいた、そしてしばしばより微妙な理解へとシフトし、女性が先史時代においても大きな主張をせずに積極的な役割を果たしていたことを認識しています。
霊長類学は、私たちの類人猿の親戚を調査することで啓発的(そして謙虚な)文脈を提供しました。20世紀の大部分において、人類の進化のモデルは、共通のチンパンジーの観察に基づいていました。これは、男性が支配し、女性を虐待することさえある、父権的で攻撃的な男性結束社会です。これは、ホミニンの「自然な」状態が男性支配であり、初期の人類が狩猟を行う男性集団で生活していたという仮定を助長しました。しかし、ボノボ(Pan paniscus)の発見と研究はこの見解を根本的に覆しました。1990年代から、霊長類学者エイミー・パリッシュらは、ボノボが女性中心であることを強調しました。「ボノボは女性が支配し、性的接触を社会的接着剤として使用します。そして重要なのは、女性が無関係な女性とさえ強い絆を形成することです。」ボノボのグループでは、男性は暴力的ではなく、しばしば最下位に位置し、高位の年長女性とその同盟が平和を維持しています。この発見は、チンパンジーとボノボが遺伝的に同等に近いにもかかわらず、反対の社会構造を持っているという「驚くべき結論」であり、私たちの系統における父権制の必然性を再考させました。科学ライターのアンジェラ・サイニが指摘するように、ボノボは自然界における母系モデルが存在することを示し、人類の祖先について新たな疑問を提起しました:初期のホミニン社会はチンパンジーのものよりも男性支配が少なかったのか?協力的な女性ネットワークが鍵だったのか?人間はボノボではありませんが、この洞察は多様性への理解を開きました。また、クリス・ナイトのような進化における女性の連合とセクシュアリティを強調する仮説に信憑性を与え、霊長類グループにおける女性リーダーシップがどのように機能するかの自然な類推を提供しました。
進化生物学と古人類学も同様に、過去の女性の役割を評価し始めました。影響力のあるアイデアの一つは、クリステン・ホークスらによって提案された「祖母仮説」であり、人間の長寿(特に閉経と女性の長い生殖後の寿命)が、祖母が孫の生存に重要な貢献をしたために進化したとしています。この仮説によれば、初期のホモ・サピエンスのコミュニティでは、もはや子供を産むことができない年長の女性が孫の養育と世話を助け、その娘が次の子供を早く持つことを可能にしました。この祖母の実践は、グループ全体の生殖成功を高めるでしょう。これは、支援的で知識豊富な女性の存在が人間の生活史の進化の推進力であったことを示唆しており、基本的に多世代家族と協力的な子育ての人間の「条件」は先史時代の祖母に負うところがあるとしています。最近の研究では、祖母の近くに住むことの進化的利益(例:子供の死亡率の低下)が実際に見つかっています。このような発見は物語を変えます:進化の英雄としての男性ハンターではなく、我々の種の成功を確保する無名の英雄としての女性の共同親(共同母または祖母)がいます。
協力的な繁殖のテーマは、人間が「世話をする類人猿」であり、各子供を育てるために多くの助けを必要とするというもので、人類学者サラ・ブラファー・ハーディによって提唱されました。ハーディは、初期の人類の母親は、単独で大きな脳と長い幼年期を持つ子供を離乳し育てることができなかったと主張し、親族(祖母や年長の子供を含む)からの支援が必要だったとしています。これは、私たちの祖先の間で共感、コミュニケーション、社会的知性の前例のないレベルを促進しました。興味深いことに、この論理は文化の起源に戻ります:もし人間の乳児が必要で社会的であり、母親が助けを求めるならば、社会的協力とおそらく言語の非常に基礎は母子(および母親と親族)の相互作用にあるかもしれません。実際、最近の学者スヴェルケル・ヨハンソンは、ハーディの研究に基づいて、言語の進化が女性の協力に多くを負っているかもしれないと提案しています。彼は、男性の交尾競争に焦点を当てた理論が証拠に合わないことを指摘しています:「言語が性的選択を通じて進化したという一般的な仮説、つまり男性が女性の注意を引くために競争するという仮説は却下できます。女性と男性は同じように話します。そしてそれは、言語の説明が性別に中立であるか、ほぼそうでなければならないことを意味します。」代わりに、ヨハンソンは、言語が子育てや他の社会的タスクにおけるグループ全体の協力を促進するために発展したと仮定しています。彼は「チンパンジーテスト」と呼ぶものを導入し、言語の起源の理論は、なぜ他の霊長類(バブーンやチンパンジーのような)が言語を進化させなかったのかを説明しなければならないとしています。彼の答えは、初期の人類が独自の状況を持っていたというもので、おそらく難しい出産と助産の必要性に関連しているかもしれません。彼は、人間の赤ちゃんが二足歩行と大きな脳のためにしばしば出産時に助けを必要とし、新生児が無力であるという事実を指摘しています。したがって、助産師や祖母が彼のシナリオで重要な役割を果たします。ヨハンソンの見解では、言語は最初に女性(母親や他の世話人)の間で、互いに助け合うためのコミュニケーションシステムとして発展した可能性があります(「今押して!」「水を持ってきて!」または赤ちゃんを落ち着かせるために)。多くの世代にわたって、これらの母親の発声はより精巧になり、コミュニティ全体で共有されるようになった可能性があります。これは、以前に人類学者ディーン・フォークが提案した「母語仮説」と強く共鳴します。フォークは、初期のホミニンの母親が食料を探すために赤ちゃんを置かなければならなかったとき、彼らはメロディックな発声(子守唄や落ち着かせるスピーチの前兆)で赤ちゃんを安心させ、落ち着かせたと提案しました。これらの感情的な音は、基本的に古代の母親語の形であり、徐々に意味と構造を獲得し、真の言語の基礎を築きました。時間が経つにつれて、母と子の間のコミュニケーションとして始まったものは、より広い家族やバンドに拡大し、すべての人が共有する完全な言語になりました。
このような仮説は、女性の社会的および育児活動が人間の象徴文化の進化において推進要因であった可能性があることを強調しています。それらはロマンチックな神話ではなく、現実的な進化生物学に基づいていますが、それでも女性の重要性を人間の物語において高めています。
もう一つの興味深い分野は、革新と技術です。考古学的には、最も初期の文化的発明のいくつかは女性から来た可能性があります。たとえば、容器(編みかご、陶器)の発明は、旧石器時代や中石器時代の多くの文脈で、女性であると考えられる採集職人に帰されることがよくあります。新石器時代の農業の発展は、種を植えることを試みた女性の採集者によって始められたと広く考えられています。動物の家畜化も、小動物の扱い手や孤児の動物の世話をする人としての女性に何かを負っているかもしれません。直接的な証拠は乏しいですが、シュミットの観察と一致しています。「女性は植物の最初の栽培に関与しており、これが彼女たちの社会的重要性を高め、初期の農耕コミュニティでの女神崇拝を生み出した可能性がある」と述べています。火の制御と料理の発明さえも、人間文化の重要なマイルストーンであり、女性の努力に部分的に帰されることができます:霊長類学者リチャード・ランガムの「料理仮説」は、食べ物を調理するための火の習得が人間の進化にとって決定的であったと主張しており、多くの採集社会では、女性が炉の主な管理者であり、植物食品の知識を持っています。水を沸かしたりヤムイモを焼いたりしたのがどちらの性別であるかはわかりませんが、先史時代の料理において女性の栄養士が男性の狩猟者と同じくらいの役割を果たしたと考えるのは合理的です。
文化の誕生の中心に女性を置く現代の理論の一つは、クリス・ナイトの挑発的な作品です。『Blood Relations: Menstruation and the Origins of Culture』(1991年)で、ナイトは人類学、進化生物学、神話を統合し、最初の人間の象徴文化が女性の連帯によって創造されたと主張しています。「性ストライキ」のアイデアに基づいて、ナイトは、初期の人間の女性が排卵と月経を同期させ(おそらく月の周期を時計として使用し)、特定の時期に男性への性的アクセスを集団的に拒否し、男性が狩猟と肉の共有に協力することを強制したと提案しています。ナイトの仮説によれば、これが最初の儀式と禁忌を生み出し、たとえば月経の禁忌、血を象徴する赤く塗られた体、時間を「女性」(禁止)と「男性」(開放)フェーズに儀式的に分割することなどです。彼は、後期旧石器時代(約40,000年前)に、この女性主導のストライキと祝賀のダイナミクスが、多くの考古学者が特定する「象徴革命」(芸術、個人装飾、複雑な埋葬儀式の急増など)を促進したと想像しています。ナイトのシナリオでは、女性の集団行動が社会契約を築き、狩猟者が肉を持ち帰り、月経後の祝宴で分配され、性別間の新しいレベルの同盟を築きましたが、女性の条件で行われました。ある要約によれば、ナイトは「女性が性と月経のリズムを通じて文明の原初の創造的衝動を育み、彼女たちが本質的に人間文化を創造した」と主張しています。ナイトが集めた証拠は、創造神話の共通点(彼はアボリジニのワウィラク姉妹の神話を、月経の同期と儀式の起源の寓話として分析しています)から、狩猟採集者や霊長類の行動まで多岐にわたります。多くの人類学者はナイトの理論を推測的と見なしていますが、それは生物学的な類人猿が文化的な人間になる方法を説明しようとする真剣な試みであり、その移行の閃光点に協力的な女性のグループを置き、社会を可能にするルールとシンボルを発明したとしています。
別の観点から、既存の社会の民族誌的および社会学的研究は、祖先のパターンを反映しているかもしれない強力な女性の役割を時折明らかにします。人類学者ペギー・リーブス・サンデイは、彼女の文化横断的調査『Female Power and Male Dominance』(1981年)で、女性が財産、相続、儀式を大いに管理する社会(西スマトラのミナンカバウや特定のネイティブアメリカンのグループなど)をいくつか特定しましたが、彼女たちは正式に男性を支配していません。サンデイはこのようなケースを慎重に「母系社会」と定義し、鏡像の父権制ではなく、女性の利益が社会的事柄で優勢である設定として定義しました。彼女は、厳密に母系社会である既知の社会はないが、女性の地位のスペクトルが存在し、いくつかの文化は確かに女性中心と呼ぶことができると結論付けました。中国のモソ族(母系家族と歩き婚を持つ)やアルジェリアのカビール神話の女性聖人のような現代の例は、女性中心の社会組織が純粋な幻想ではないことを示していますが、どのケースでも、男性が政治的または物理的な力を持っているため、父権制の真の逆転を防いでいます。
重要なのは、今日の科学的コンセンサスは、文字通りの意味での過去の母系文明の概念を支持していないことです。支持しているのは、女性が常に人類の物語に不可欠であったという見解です。採集者や革新者として、文化や言語の担い手として、そして重要な社会的変革における平等なパートナー(場合によってはリーダー)として。ブリタニカ百科事典が簡潔に述べているように、「女性が集団として男性を集団として支配した社会の証拠はまだ見つかっていません。」しかし、女性が宗教的または経済的に重要な役割を果たした母系親族社会の初期社会の証拠は豊富に存在し、進化論はますます女性の主体性(配偶者選択、育児、協力を通じて)を人間の進化の推進力として認識しています。要するに、強い形での「文化の母」仮説は未だ証明されていませんが、弱い形では—母親や祖母、賢い女性や女神が常に人間であることの基盤にあった—それはかなりの支持を得ています。
結論#
女性が人間の条件の創始者であり文化の創設者であったという考えは、神話から推測、科学的分析へと複雑な旅をたどってきました。それは神聖な物語の領域で始まりました:世界を生み出し、法律を授け、芸術を教えた女神や最初の女性の物語。19世紀には、バッホーフェンのような学者がこれらの物語を歴史の壮大な理論に変え、女性の影響が最高であり、人間文化が母権から生まれた実際の時代を想像しました。この大胆な仮説は、多くの人々を魅了しました—モーガン、エンゲルス、その他—彼らはそれを新たな知識と組み合わせて、初期の社会が女性中心であり、私有財産や新しい神々がバランスを崩すまで続いたと主張しました。時間が経つにつれて、証拠とイデオロギーの風向きが変わりました。人類学者は単純な普遍的な母系社会を否定するデータを集めましたが、その概念の魅力は続き、各時代の関心事によって再形成されました:ビクトリア朝の父権制の擁護者はそれを否定し、全体主義体制はそれを利用または歪め、フェミニスト運動はそれを力を与える神話として再発明し、人類学者は霊長類の行動、化石、親族研究のレンズを通して再検討しました。
この歴史から浮かび上がるのは、文字通りの母系王国を必要としない人間の進化における女性の役割の豊かな評価です。女性は創造者として—生命の創造者であることはもちろんですが、また生計戦略、慰めの言語、共有のネットワーク、神聖な意味の創造者として—常に我々の種の中心にいました。私たちの理解が深まるにつれて、女性が文化の側面の創始者であったかどうかではなく、どのように、どのような方法でそうであったかが問題となります。現代の研究は、長い幼年期(したがって教育)、協力的な繁殖、コミュニケーションのような発展が、Y染色体と同じくらいX染色体に依存していた可能性があることを示唆しています。神話の「最初の女性」は一人で支配していなかったかもしれませんが、彼女と彼女の実生活の対応者である初期のホモの中の女性たちは、人間の物語を形作るのを助けました—痕跡を残さずに消えた黄金の母系社会ではなく、各新世代を育て、文化を可能にする絆を維持するという永続的で不可欠な仕事の中で。
参考文献 #
古典的な「母系社会論争」#
- ヨハン・ヤコブ・バッホーフェン、Das Mutterrecht(1861年)
- バッホーフェンとその後の受容に関する百科事典の概要
- ルイス・ヘンリー・モーガン、Ancient Society(1877年)
- フリードリヒ・エンゲルス、The Origin of the Family, Private Property and the State(1884年)
- サー・ヘンリー・S・メイン、Ancient Law(1861年)
- ジョン・F・マクレナン、Studies in Ancient History(1886年)
- エドヴァルド・ウェステルマルク、The History of Human Marriage(1891年)
- ジェーン・エレン・ハリソン、Prolegomena to the Study of Greek Religion(1903年)
- ジェーン・エレン・ハリソン、Themis(1912年)
- ロバート・ブリフォールト、The Mothers(1931年)
- ブロニスワフ・マリノフスキ、Sex and Repression in Savage Society(1927年)
- ヴィルヘルム・シュミット、The Origin and Spread of the World Cultures(1930年)
- A. R. ラドクリフ=ブラウン、「南アフリカにおける母の兄弟」(1924年)
- E. E. エヴァンス=プリチャード、「王権の初期の歴史に関するいくつかの考察」(1930年)
- アルフレッド・バウムラーとアルフレッド・ローゼンベルク – ナチス時代のバッホーフェンの受容(概要)
- シンシア・エラー、The Myth of Matriarchal Prehistory(2000年)
- マリヤ・ギンブタス、The Goddesses and Gods of Old Europe(1974年)
- エリザベス・グールド・デイヴィス、The First Sex(1971年)
- マーリン・ストーン、When God Was a Woman(1976年)
- ペギー・リーブス・サンデイ、Female Power and Male Dominance(1981年)
- シモーヌ・ド・ボーヴォワール、The Second Sex(1949年)– 母系社会神話の批判
- ジョーン・バンバーガー、「母系社会の神話:なぜ原始社会で男性が支配するのか」(1974年)
霊長類学、育児と言語進化の視点#
- エイミー・パリッシュ、「ボノボ(Pan paniscus)における女性の関係」(1996年)
- クリステン・ホークスら、「祖母、閉経、人間の生活史の進化」(1997年)PNAS
- サラ・ブラファー・ハーディ、Mothers and Others(2009年)
- スヴェルケル・ヨハンソン、The Dawn of Language(2021年)
- ディーン・フォーク、「初期ホミニンにおける前言語進化:母親語はどこから来たのか?」(2004年)
- クリス・ナイト、Blood Relations: Menstruation and the Origins of Culture(1991年)
FAQ#
Q 1. 「原初の母系社会」仮説とは何ですか? A. これは、1861年にJ.J.バッホーフェンによって普及され、その後の思想家によって支持された理論で、初期の人間社会が普遍的に女性が社会的、政治的、または精神的な力を持っていた段階(「母権」)を経て、父権制に取って代わられたというものです。
Q 2. 古代の母系社会の科学的証拠はありますか? A. いいえ。多くの神話には強力な女性の人物が登場し、いくつかの社会は母系または母系中心ですが、人類学者や考古学者の間での学術的コンセンサスは、女性が集団として男性を集団として体系的に支配した過去の時代を確認する証拠はないというものです。この概念は現在、歴史的理論または神話そのものとして見られています。
Q 3. 母系社会が存在しなかった場合、今日の学者は文化の起源における女性の役割をどのように見ていますか? A. 現在の研究は、具体的で証拠に基づいた貢献に焦点を当てています:「祖母仮説」(女性の長寿が子孫の生存を助けた)、農業や初期技術(陶器、織物)の発明における女性の役割、言語の起源における母子コミュニケーションの重要性(母親語仮説)、霊長類学が示唆する女性の社会戦略(例:ボノボ研究)などです。女性は進化と文化の中心的な主体と見なされていますが、失われた母系世界の支配者ではありません。