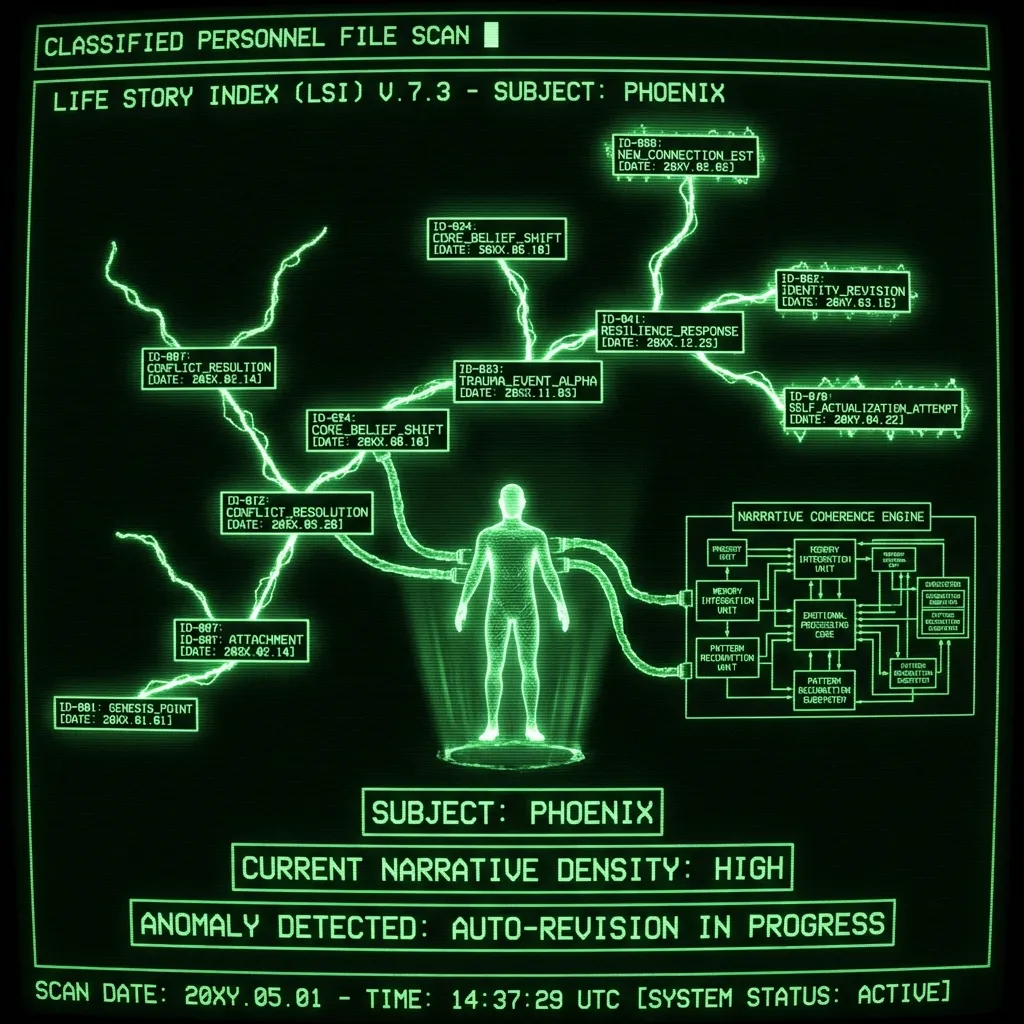TL;DR
- 「ナラティブ・セルフ」理論は、個人のアイデンティティが固定された実体ではなく、私たちの人生について構築する継続的な物語であると主張します。
- 主な提唱者には、デネット(「ナラティブ重力の中心」としての自己)、リクール(ナラティブ・アイデンティティ)、マクアダムス(ライフストーリーモデル)、ブルーナー(ナラティブモード)、ガザニガ(左脳の解釈者)が含まれます。
- 神経科学は、脳の左半球とデフォルトモードネットワークがこれらの自己ナラティブの生成に関与していることを示唆しています。
- 記憶は現在のナラティブに役立つ再構成プロセスと見なされ、自己の連続性を助けますが、歪みを許します。
- 批判として、特にガレン・ストローソンからは、すべての人が人生をナラティブとして経験するわけではない(「エピソディック」対「ダイアクロニック」個人)と主張し、この理論を普遍化すべきではないとしています。
- この概念は、アイデンティティ、エージェンシー(潜在的に幻想的)、記憶、意識の理解に影響を与え、治療に応用されています。
はじめに#
近年、哲学、心理学、認知科学、神経科学、文学理論の多くの学者が、自己が本質的に私たちの人生について構築する物語またはナラティブであるという考えに収束しています。この「ナラティブ・セルフ」観において、個人のアイデンティティは固定された本質ではなく、私たちの経験、記憶、解釈から織り成される継続的な自伝です。認知心理学者ジェローム・ブルーナーが言ったように、「自己は絶えず書き直される物語」であり、最終的には「私たちが自分の人生について『語る』自伝的ナラティブになる」のです。哲学者ダニエル・デネットもこれに共鳴し、「私たちは皆、名人級の小説家であり…すべての素材を一つの良い物語にまとめます。そしてその物語が私たちの自伝です。その自伝の中心にいる主要な架空のキャラクターが自己です」と述べています。この文献レビューでは、ナラティブ・セルフの概念の発展を学際的に調査し、その定義と理論的基盤、主要な提唱者(例:デネット、リクール、マクアダムスなど)、バリエーションと批判(例:ガレン・ストローソンの反対意見)、実証的な発見、およびアイデンティティ、エージェンシー、記憶、意識の理解に対する広範な影響について考察します。
ナラティブ・セルフの哲学的基盤
初期の哲学的洞察#
アイデンティティがナラティブに結びついているという考えは、何世紀にもわたる哲学的な根源を持っています。ジョン・ロック(17世紀)は、個人のアイデンティティが意識と記憶の連続性に基づいていると提案しました。これは本質的に、自分自身について思い出せる「物語」です。デイヴィッド・ヒューム(18世紀)はさらに進み、私たちの知覚の下に固定された自己は存在せず、自己は想像力によって結びつけられた知覚の「束」であると主張しました。私たちは架空の連続性を創り出し、自己が一種のナラティブ構築である可能性を早くから示唆しました。20世紀には、哲学者アラスデア・マッキンタイアが「人間の人生の統一性」はナラティブの統一性を持ち、人生の善や意味を問うことは本質的にその人生の物語(生きているナラティブの探求)を問うことであると主張しました。このような視点は、20世紀後半の哲学における明確なナラティブ・セルフ理論の舞台を整えました。
ナラティブ・アイデンティティと解釈学(ポール・リクール)#
フランスの哲学者ポール・リクールは、1980年代に現象学、解釈学、文学理論を橋渡しする形でナラティブ・アイデンティティの概念を発展させました。リクールは、私たちのアイデンティティ(「私たちが誰であるか」)は静的な存在ではなく、私たち自身について語る物語を通じて構成されると主張します。彼の見解では、すべての自己認識は解釈的な行為であり、「ナラティブにおいて…特権的な媒介を見出す」としています。彼は、個人のアイデンティティが歴史とフィクションの交差点で生まれると仮定し、実際の出来事と想像された解釈を織り交ぜて一貫した人生の物語を作り上げるとしています。リクールは、「人間の人生は、それについて語られる物語の光の中で解釈されるとき、より容易に理解可能になるのではないか?…自己認識は解釈であり、自己解釈はナラティブにおいて…特権的な媒介を見出し…人生の物語をフィクションの物語または歴史的フィクションに変える」と述べています。要するに、リクールにとって自己は本質的にナラティブであり、私たちは継続的な物語の中で自分を主人公として位置づけることで存在を理解します。この見解は文学理論にも影響を与え、自伝文学や物語の研究を自己理解の鍵として正当化しています。
「ナラティブ重力の中心」としての自己(ダニエル・デネット)#
認知哲学において、ダニエル・デネットはナラティブ・セルフの主要な提唱者です。デネットは、内部に「不変の魂」や単一の形而上学的自我が存在するという考えを否定し、自己を私たちのナラティブ解釈における架空の重力の中心に例えています。物体の重心が有用な抽象概念であるのと同様に(具体的なものではなく、物体の質量分布によって定義される点)、自己は経験の物語によって定義される抽象的なナラティブ重力の中心です。私たちは、脳内で発生する多様な知覚、記憶、行動を理解するために、一貫した主人公を投影します。「理論家のフィクション」としての自己は、脳が経験と空想を一つにまとめ、名前で呼ばれる脳と身体に結びつけられたものです。デネットは、「あなたが何であるかは、経験と空想の転がる合計であり…一つの脳と身体に結びつけられ、名前で呼ばれるものです。加えて、あなたの特別で不溶な核があるという考えは魅力的な空想ですが、人々を理解するために必要なものではありません」と説明しています。デネットの有名な表現では、脳は著者であり、「主人公 – 自己 – は脳が語る架空のキャラクター」です。したがって、デネットの視点から見ると、自己は私たちの行動に対する有用な説明的中心を提供する抽象的な物語として存在し、具体的な実体として存在するわけではありません。
ナラティブ自己構成(マリヤ・シェヒトマンとその他)#
現代の分析哲学者たちはこれらのアイデアを基にしています。例えば、マリヤ・シェヒトマンのナラティブ自己構成理論は、個人のアイデンティティが本質的に構築された自伝的ナラティブによって創られると主張します。人は「自伝的ナラティブを形成することによって自分のアイデンティティを創造する」とし、経験を意味のある方法で結びつけます。この見解では、時間を超えて同じ人であることは、経験を継続的な物語に織り込み、自己を主役として位置づけることです。ナラティブは心理的連続性を提供し、現在の自己が過去からどのように続いているかを(自分自身や他者に)説明します。同様に、哲学者J.デイヴィッド・ヴェレマンは「私たちは自分自身を発明する…しかし私たちは本当に発明したキャラクターである」と強調し、「私たちが『誰であるか』について作り上げた物語が私たちの現実になる」と述べています。
道徳的および存在的ナラティブ(マッキンタイアとその他)#
道徳哲学において、ナラティブはエージェンシーと倫理に不可欠と見なされています。アラスデア・マッキンタイアは、良い人生を送ることは一貫したナラティブを著すことに似ていると主張しました。「人間の人生の統一性は、単一の人生に具現化されたナラティブの統一性です」。私たちは、人生を物語として見ることで初めて行動を理解し、倫理的に評価することができます(目標、転換点、目的を持つナラティブの連続性)。存在哲学や文学においても、自己をナラティブとして認識することがあります。例えば、ジャン=ポール・サルトルは、人々が自分を定義するために絶えず物語を織り成していると述べ(ただししばしば悪い信仰で)、マルセル・プルーストのような小説家は、アイデンティティが人生の物語を通じてどのように展開し、修正されるかを示しました。
表1 – ナラティブ・セルフに関する代表的な思想家(学際的)#
| 思想家(分野) | ナラティブ・セルフの主要な考え |
|---|---|
| ダニエル・デネット(哲学 / 認知科学) | 自己は抽象的な「ナラティブ重力の中心」であり、私たちの脳が人生の物語を組織する架空の点です。私たちは名人級のストーリーテラーであり、すべての経験を自伝的ナラティブにまとめます。 |
| ポール・リクール(哲学 / 文学理論) | ナラティブ・アイデンティティ:アイデンティティは私たちが自分自身について語る物語を通じて構成されます。自己認識は本質的に歴史とフィクションを組み合わせた解釈的ナラティブ行為です。 |
| マリヤ・シェヒトマン(哲学) | ナラティブ自己構成:個人のアイデンティティは、経験と意図を時間を超えて結びつける一貫した自伝的ナラティブを構築することによって創られます。 |
| J. ブルーナー(心理学) | 自己は物語です。人々は自然に記憶や経験をナラティブ形式で整理し、一貫性と意味を生み出します(「人生を物語として」)。 |
| ダン・P・マクアダムス(心理学) | ナラティブ・アイデンティティ:各人は統一性と目的を提供する「内面化された人生の物語」を発展させます。マクアダムスは「私たちは皆ストーリーテラーであり、私たちは語る物語です」と述べています。 |
| マイケル・ガザニガ(神経科学) | 脳の左半球は「解釈者」として機能し、行動や経験を説明するために絶えずナラティブを作り出し、統一された自己の幻想を与えます。 |
| アントニオ・ダマシオ(神経科学) | 「自伝的自己」は個人的な記憶と計画から構築され、本質的にコア自己を時間的に拡張し、過去と未来をアイデンティティの一部として解釈するナラティブです。 |
| トーマス・メッツィンガー(哲学 / 神経科学) | 自己は物ではなく、脳によって生成されるモデルです。「ナラティブ・セルフ」は脳の自己モデルが維持する高次の仮想アイデンティティ(継続的な物語)であり、実際には「そのような自己は存在しない」としています。 |
| J. デイヴィッド・ヴェレマン(哲学) | 私たちは物語の中でキャラクターを発明することによって自分自身を発明し、そしてその架空のキャラクターになります。自己はパフォーマティブなナラティブ構築です。 |
| アラスデア・マッキンタイア(哲学) | 人生にはナラティブの統一性があります。個人のアイデンティティと倫理的な生活は、人生を一貫性と方向性を持つ物語(探求)として考えることを必要とします。行動はこのナラティブ全体の文脈でのみ意味を持ちます。 |
| オリバー・サックス(神経学 / 文学) | 「私たちのそれぞれが物語を構築し、その物語が私たちです」と神経学者オリバー・サックスは書いており、脳損傷を受けた患者でさえしばしば経験にナラティブの秩序を回復しようとすることを観察しました。 |
表1: 自己が物語のような性質を持つと主張する様々な分野の思想家たち。
ナラティブ・セルフに関する心理学的視点
パーソナリティ心理学におけるナラティブ・アイデンティティ#
心理学では、自己のナラティブ概念が特にパーソナリティ心理学や発達心理学で非常に影響力を持っています。例えば、ダン・マクアダムスは、アイデンティティのモデルを開発し、「ライフストーリー」がパーソナリティの中心的なレベルであるとしています(特性や動機の上に)。マクアダムスによれば、成人初期までに個人は過去を結びつけ、未来を予測する個人的な神話または人生の物語を内面化し、統一性と目的を提供します。彼はナラティブ・アイデンティティを「自分自身について作り上げる内面化された物語 – 自分自身の個人的な神話」とし、設定、シーン、キャラクター、プロットを備え、時間とともに進化すると述べています。マクアダムスの言葉を借りれば、人間は「自分自身について語る物語によって生きるストーリーテリングの生き物」です。この人生の物語は、人々が経験を解釈するための枠組みを提供します(例えば、困難を「人生の第3章で克服した挑戦」として見る)。マクアダムスや他の研究者による研究は、個人の人生の物語のテーマが幸福と関連していることを示しています。例えば、苦しみを成長や良い結果につながるものとして捉える「贖罪の物語」は、より高い生活満足度と生成性と関連し、良い時が悪くなる「汚染の物語」は、より低いメンタルヘルスと関連しています。このような発見は、人生をどのように語るかがアイデンティティと幸福に大きく影響する可能性があることを支持しています。
認知および発達心理学#
認知心理学者ジェローム・ブルーナーは、ナラティブ心理学の先駆者です。彼は、人間にはナラティブモードと呼ばれる基本的な思考様式があり、物語を構築することで世界を理解すると主張しました(「パラダイマティック」または論理科学的思考様式とは異なる)。ブルーナーは、幼少期から人々は記憶を整理し、人生をナラティブ形式で理解すると提案しました。「私たちは散在する経験に一貫性を持たせるために、人生のエピソードを物語にまとめる」と述べています。発達研究は、子供たちが幼児期(3〜5歳頃、言語と自己概念が成長するにつれて)に自伝的記憶や簡単な人生の物語を形成し始めることを支持しています。親が子供と一緒に物語を語ること(過去の出来事を再現すること)は、子供たちが出来事を因果的な順序に並べるのを助け、効果的に自己のナラティブ構築を教えます。時間が経つにつれて、これらの物語はより複雑になり、より広範な人生の期間(例:「学校にいたとき」、「都市に引っ越した後」)を統合し、全体的な物語に発展します。青年期や成人期には、ほとんどの人が自分の人生の合理的なナラティブを語ることができ、心理学者はこれを健全なアイデンティティ発達の特徴と見なしています。
記憶と自己の連続性におけるナラティブ#
心理学者たちはまた、記憶が能動的で再構成的なプロセスであり、過去の完璧な記録ではなく、むしろ自己の「回顧録」を絶えず編集するストーリーテラーのようであると指摘しています。フレデリック・バートレットの古典的な実験(1932年)は、人々が既存のスキーマやストーリーラインに合うように出来事の記憶を自然に再形成し、「奇妙な詳細」を無意識に変更して「意味を持たせる」ことを示しました。これは、私たちの記憶システムが一貫したナラティブを求めていることを示唆しています。特に自伝的記憶は偏りがあり選択的です:私たちは自己イメージに合う重要な瞬間を強調し、合わないものを忘れたり歪めたりし、さらには無意識に説明を発明して点を結びつけます。このストーリーテリング記憶は連続性の感覚を維持するのに役立ちます – まるで自己の物語の個人史セクションを絶えず修正して、自己のイメージと一致させているかのようです。研究は、より一貫した人生の物語を持つことがより大きな心理的幸福と関連していることを発見しました。ある研究は、「一貫した自伝的ナラティブを構築することが心理的幸福と関連している」と確認し、特にそれらのナラティブが人生のエピソードの意味と統合を提供する場合にそうです。対照的に、物語の断片化(過去の出来事を理解するのが難しい、または連続性を感じるのが難しい)は、アイデンティティの混乱や精神的苦痛と関連しています。この心理学の証拠のラインは、ナラティブ・セルフモデルを実証的に支持しています:人生を物語として見ること(そしてその物語を一貫して表現できること)は、安定したポジティブなアイデンティティの重要な部分であるようです。
臨床および社会心理学 – 治癒と文化におけるナラティブ#
ナラティブアプローチは臨床心理学やセラピーにも現れます。マイケル・ホワイトとデイビッド・エプストンによって開発されたナラティブセラピーは、自己を物語として明示的に扱い、クライアントが生きるナラティブを「再著作」することを奨励し、変化の可能性を開きます。例えば、「私は失敗者だ」というアイデンティティに囚われている人は、成功やレジリエンスを強調する方法で物語を再構築することで、自己概念を変えることができます。同様に、トラウマセラピーでは、トラウマ体験の一貫したナラティブを構築することがしばしば治癒に役立ちます – 混沌とした記憶を構造化された物語に変えることで症状を軽減できます(ジェームズ・ペネベーカーのライティングセラピー研究で見られるように)。より広い社会レベルでは、文化はマスターナラティブ – 共有されたストーリーテンプレート(例えば、宗教的な贖罪の物語や「アメリカンドリーム」の貧困からの成功物語)を提供し、個人が内面化します。社会学者や異文化心理学者は、自己のナラティブモードが異なる可能性があることを観察しています:西洋文化はより個人主義的な自伝的ナラティブ(自分の人生をユニークな個人的な物語として見ること)を促進する傾向がありますが、いくつかの非西洋文化は家族やコミュニティの物語を通じて自己を定義する集団的または相互依存的なナラティブを強調します。それにもかかわらず、人生の物語を作る行為は人間の普遍性であるように見えますが、その物語の内容やスタイルは文化によって異なることがあります。
認知科学と神経科学: 脳のストーリーテリング#
図1: 脳の左半球と右半球。神経科学者マイケル・ガザニガの分離脳研究は、行動や感情を理解するためにナラティブを作り出す「左半球の解釈者」を明らかにしました。これは、脳の左側が絶えず説明を生成していることを示唆しており、効果的に統一された自己の感覚を作り出すストーリーテラーです。
現代の神経科学は、脳が自己の感覚を作り出すために文字通りナラティブを構築しているという興味深い証拠を提供しています。マイケル・ガザニガは、分離脳研究で「左脳の解釈者」と呼ばれるものを発見しました。脳の半球が外科的に分離された患者において、ガザニガは左半球(言語を制御する)が右半球によって開始された行動に対して説明を発明することを観察しました – 本質的に、合理的な行動の物語に合うように即興で作られた説明です。例えば、患者の右半球(話すことができない)が何かをするように指示され(例えば、部屋を出る)、その後左半球にその理由を尋ねられた場合(真の理由を知らない)、患者は即座に「オー、ソーダが欲しかったから」といった理由を作り出すかもしれません。左半球はこのようにオンラインのナレーターとして機能し、持っている情報を取り、秩序と意味を課します:「左半球は…すべてを物語に適合させ、文脈に入れようとします。パターンが存在しない証拠があっても、構造について仮説を立てることに駆り立てられているようです」。ガザニガの言葉を借りれば、「これは私たちの脳が一日中行っていることです。入力を取り…それを物語に合成します。事実は素晴らしいですが、必要ではありません。左脳は残りを即興で作ります」。この神経学的証拠は、ナラティブ・セルフの考えを強く支持しています:単一で一貫した自己であるという感覚は、主に左半球の言語センターで脳内で進行中のストーリーテリングプロセスである可能性があります。私たちは、自己の多くのモジュールプロセスから一貫した「私」の感覚を織り成す解釈的なナレーターを持ち歩いています。興味深いことに、この解釈者は、存在しないエージェンシーのナラティブさえ作り出すことができます – 例えば、実験者によって誘発された行動を選んだと確信している人々が、その理由を自信を持って語る実験のように。このような発見は、脳が強迫的な意味生成者であり、一貫した自己の幻想を維持するために個人的なナラティブを生成していることを強調しています。
脳のデフォルトモードネットワークと「内部ナラティブ」#
休息状態の脳活動の神経科学も、自己概念におけるストーリーテリングを示唆しています。外部のタスクに集中していないとき – 例えば、ぼんやりとした空想や回想中に – 脳のデフォルトモードネットワーク(DMN)が非常に活性化されます。DMNは、自己参照的思考、記憶の検索、未来の展望に関連する中線領域(内側前頭前野と後部帯状回/楔前部を含む)のセットです。特に、研究者たちはDMNを自己の感覚を維持するために重要な「内部ナラティブ」を作り出すものとして特徴づけています。休息や心のさまよい中に、人々はしばしば過去や未来のシナリオに自分自身を投影します – 本質的に、彼らはナラティブを生成します(例えば、出来事を再現したり、会話を想像したり、将来の計画をスクリプト化したりします)。これにより、科学者たちは「DMNは自己の感覚を構築するのに役立つ一貫した内部ナラティブを作り出す」と提案しています。言い換えれば、脳のデフォルト活動は、過去の記憶と未来のシミュレーションを現在の自己イメージと統合する物語を織り成すことです。これは、自己伝記的記憶と未来の計画が密接に関連しているという認知理論と一致しています:私たちは、過去の自分を覚えるためだけでなく、物語作りによって未来の行動を予測し導くために同じナラティブ能力を使用します。研究はまた、DMNが個人のアイデンティティや特性について明示的に考えるように求められたときや、人生のエピソードを思い出すときに関与していることを示しています – これにより、ナラティブ・セルフの物理的基盤がこれらの脳ネットワークにある可能性が示唆されます。このネットワークの一部が損傷または混乱すると(アルツハイマー病のように)、しばしばナラティブの連続性に混乱が生じます(例えば、自伝的記憶の喪失や未来を想像するのが難しい)、これによりDMNの活動がナラティブ・セルフを維持する能力に関連していることがさらに示唆されます。
記憶と想像の神経科学#
他の認知神経科学の研究は、記憶の再生が文字通りの再生ではなく、しばしば現在の自己ナラティブに役立つ再構成であることを発見しました。エリザベス・ロフタスの偽記憶に関する研究は、自己の物語や期待に合う場合に、人々が実際には起こらなかった出来事を「思い出す」ように簡単に誘導されることを示しています。また、神経イメージングは、出来事を思い出すときと仮想の出来事を想像するときに、多くの同じ脳領域が活性化することを明らかにしています – 両方の場合において、私たちは実質的に物語を構築しています。これにより、記憶が未来志向であるという理論が生まれました:私たちは過去を知るためだけでなく、物語作りによって未来の行動を予測し導くために、記憶の断片(記憶)を維持しています。したがって、認知科学の観点から、ナラティブ・セルフは時間を超えて自分自身の活動を理解しようとする脳の努力から生じます。それは一種のユーザー幻想またはインターフェースであり、膨大な並列分散型の神経システムが自分自身を連続性と目的を持つ単一の存在として扱うことを可能にする簡略化された「私」の物語です。
自己モデル理論(メッツィンガー)と自己の幻想#
哲学者で神経科学者のトーマス・メッツィンガーは、ナラティブ・セルフと一致する理論的枠組みを提供しながら、自己を持つことに関する直感に挑戦しています。『Being No One』(2003年)で、メッツィンガーは、私たちが考えるような実際の自己は存在しないと主張し、代わりに脳が感覚、認知、記憶情報を統合する現象的自己モデル(PSM)を生成すると述べています。この自己モデルは「透明」であり、モデルであることに気づかず、自己として経験します。自己モデルの層の中で、他者がナラティブ・セルフと呼ぶものは、時間を超えて経験を統合する高次の部分(しばしば言語的および概念的)と見なすことができます。メッツィンガーは、最小限の自己(任意の瞬間における即時的で反射的でない「私」の感覚で、意識に密接に結びついている)とナラティブ・セルフ(個人の歴史や計画を含む拡張された自己モデル)を区別します。ナラティブ・セルフは、本質的に、自己モデルがその生物について語る物語です。メッツィンガーとその同僚によれば、このナラティブ層は認知制御と一貫性を提供するのに役立ちます:それは生物が計画を立て、目標を維持し、他者に安定したアイデンティティを提示することを可能にします。しかし、メッツィンガーは、自己(ナラティブ・セルフを含む)が一種の構築された幻想であるため、それを実体化しないように注意する必要があると警告しています – 「物語」は現実のように感じられますが、それは私たちの脳が進化させたツールです。彼の立場は、「世界には自己のようなものは存在しない…存在するのは現象的自己だけである」、すなわち、私たちが経験する自己は基礎となる生物の情報処理によって生成された外観であると要約されています。これは、自己がマーヤ(幻想)であるという仏教に影響を受けた考え(およびいくつかの東洋哲学)と一致しており、ナラティブモデルと興味深く共鳴しています。なぜなら、ナラティブは表現であり、実際のものではないからです。
現象学: 最小限の自己対ナラティブ・セルフ#
現象学者のダン・ザハヴィやショーン・ギャラガーは、ミニマルまたはコアセルフとナラティブセルフを区別することで、より微細な理解を提供しています。ミニマルセルフは、第一人称の生の経験、つまり「ここに今いる」という主体としての感覚です。これは言語や記憶を必要とせず(新生児や動物でさえこの意味でのミニマルセルフを持っています)、ナラティブセルフとは対照的に、時間をかけて構築される自己概念であり、記憶、社会的文脈、想像力を必要とします。ギャラガーはナラティブセルフを「自伝的自己」(ダマシオの用語に似ている)に例え、それが発達の後期に現れ、ミニマルセルフとは独立して障害される可能性があると示唆しています(例えば、特定の脳損傷の患者は自伝的ナラティブを失うことがありますが、その瞬間の基本的な自己感覚は持ち続けます)。この区別は、ナラティブセルフの範囲に関する議論において重要です:私たちの個人的なアイデンティティの感覚がナラティブであることを認めつつも、意識を支える基本的な非ナラティブの自己(現在の瞬間の「私」または身体的自己)が存在することを認識することが可能です。実際、批評家たちは、自己のすべての側面がナラティブであるわけではないと警告しています—いくつかは身体的または経験的です。次に、そのような批判を探求します。
ナラティブセルフモデルのバリエーションと批判#
ナラティブセルフ理論は影響力を持っていますが、批判者や注意点も存在します。いくつかの思想家は、「自己を物語として見る」という考えが行き過ぎると、誤解を招いたり、過度に一般化される可能性があると主張しています。主要な批判者は哲学者のガレン・ストローソンで、彼は「ナラティビティに反対して」(2004年)という有名な論文を書きました。ストローソンは2つの主張を区別しています:心理的ナラティビティ命題(人間が自然に自分の人生を物語として見るまたは生きるというもの)と倫理的ナラティビティ命題(充実したり道徳的であるために人生を物語として生きるべきだというもの)。彼は両方を強く否定します。ストローソンは、「人間が時間の中で自分の存在を経験するための唯一の良い方法があるわけではない」ということは単に「真実ではない」と主張しています。すべての人が自分の人生を物語として考えているわけではなく、ナラティブが欠けているからといって、その人の人生が貧しいとか一貫性がないというわけではありません。彼は個人差の概念を導入します:「深く非ナラティブな人々が存在し、深く非ナラティブな良い生き方がある。」ストローソンが「エピソディック」と呼ぶ人々は、時間を超えて自分を同じ人間として強く感じることはなく、人生の壮大な物語を自然に構築しないかもしれません。彼らはより離散的なエピソードで人生を経験し、それらを統一された物語に織り込むことはありません。他の人々—「ディアクロニック」タイプ—は、現在の自己を過去や未来と密接に結びつけて見て、容易に自分の人生を物語化します。ストローソンは、ナラティビスト(多くはおそらく強くディアクロニックな性格を持つ)が、誰もが自分たちと同じだと誤って仮定し、「自分自身の経験から一般化し、[彼らが]自分にとって基本的な要素を他のすべての人にとっても基本的であると仮定する」特別な、誤った自信を持っていると主張しています。
ストローソンはさらに、ナラティブへの執着の潜在的な欠点について警告しています:それは「倫理的可能性の理解を貧弱にし」、そのモデルに合わない人々を「不必要に苦しめる」可能性があり、心理療法の文脈では「破壊的」になることさえあります。例えば、自然に自分の人生を物語化しない人に対して、そうしなければ真の人間性が欠けていると言うことは、その人を劣っていると感じさせるかもしれません。また、セラピーにおいて、「一貫した物語」を過度に強調することは、虚偽の記憶や自己の本当の感情の単純化につながる可能性があります。要するに、ストローソンは、ナラティブセルフ理論が普遍的な主張としては経験的に誤りであり、潜在的に有害であると信じています:一部の人々は深く非ナラティブでありながら、完全に人間的で道徳的に健全な生活を送っています。彼自身も「私は物語ではない」と宣言しています。この批判は多くの議論を引き起こしました。ある人々は、ストローソン自身も自分が思っている以上にナラティブに依存している可能性があると応じています(自分をエピソディックと説明する行為自体がナラティブアイデンティティの一部と見なされるかもしれません)。他の人々は、ナラティブが人間性のための全体的な要件ではないという彼のポイントを認めつつも、それが多くの人々にとって依然として一般的で有用な枠組みであると主張しています。
別の批判の角度は、自己が構築物であることに同意しつつも、必ずしもナラティブなものではないとする人々から来ています。例えば、現象学者のザハヴィ(2010年)は、ナラティブセルフモデルがミニマルセルフ—物語や反省に依存しない「私はここにいる」という基本的な感覚—を覆い隠すべきではないと主張しました。ナラティブにのみ焦点を当てると、言語以前の、身体化された自己の側面を無視する可能性があります。さらに、一部の認知科学者は、私たちの精神生活の多くが非ナラティブであると警告しています:手続き記憶、習慣、瞬間ごとの知覚は物語の形をとりません。ナラティブは、私たちが一歩引いて反省したり、コミュニケーションを取ったりするときに現れます。したがって、ナラティブセルフ理論は、自己の反省的または社会的側面を扱っている可能性があり、自己の全体性を捉えているわけではありません。
多様性とポストモダンの挑戦#
単一のナラティブという考えを複雑にするバリエーションもあります。ポストモダンやフェミニストの学者たちは、個人が文脈に応じて変化する複数のナラティブや自己物語を含む可能性があると提案しています。例えば、ある人は職業的な自己ナラティブ、家族役割のナラティブ、オンラインアバターナラティブなどを持っており、それらは完全に一貫しているわけではありません。一部のナラティブ心理学者はこれを認識し、アイデンティティを異なる文脈で語られる物語の集合として見ています—健康な自己はこれらを柔軟に交渉できる(時には多声的または対話的自己と呼ばれる)ことができるとしています。文学では、不信頼できる語り手や断片的な物語が、アイデンティティが不連続または自己矛盾していることを示すために使われてきました。これらの視点は、過度に整然とした英雄的な人生の物語を批判します;実際の人生は混乱していることがあり、きちんとした物語を主張することは、人々に本当に存在する曖昧さや内面的な葛藤を沈黙させるかもしれません。
これらの批判にもかかわらず、多くの懐疑論者でさえ、ナラティブが自己経験の重要なモードの一つであることを認めています—ただし、それを唯一または必要なモードとすることには抵抗します。ストローソンは、例えば、多くの人々が確かに「ナラティブ」な気質を持っていることを認めていますが、すべてではないとしています。ある哲学者(例えば、ソーレン・キルケゴールやニーチェ)は、人生は振り返って初めて物語として理解できるかもしれないと同意するかもしれませんが、積極的に自分の人生を脚本化することが不誠実さにつながる可能性があることを心配しています(脚本に従って生きるのではなく、自然発生的に生きる)。また、倫理的な批判もあります:ナラティブは人を閉じ込める「単一の物語」になる可能性があります(例えば、過去の出来事の被害者として自分を定義することを乗り越えられない人は、そのナラティブによって制約されるかもしれません)。これに対して、ナラティブセルフの支持者は、ナラティブ自体が修正可能であることを強調することがよくあります—自己物語は石に刻まれているわけではなく、再ナラティブ化することで、私たちは自分自身を変えることができます。
ナラティブセルフ理論の影響#
自己を基本的にナラティブとして見ることは、アイデンティティ、主体性、記憶、意識の理解に広範な影響を与えます:
- アイデンティティと連続性: ナラティブセルフモデルは、アイデンティティを固定されたコア(魂や不変の自我のようなもの)から、進行中のプロセスとして再構築します。アイデンティティは、静的な存在ではなく、生成の物語になります。これにより、変化を通じて連続性を維持する方法が説明されます:私たちの身体や好みが年々変わっても、連続した人生の物語を織り成すことで、同じ人間であるという感覚を保持します。また、アイデンティティ危機や変容のケースに光を当てます—これらは「ナラティブの修正」のインスタンスとして見られることがあります。例えば、ある人が反抗的な若者時代を、現在の知恵に至るために必要な章として再解釈するかもしれません。アイデンティティは動的で解釈的です。また、個人的なアイデンティティには、言語的で文化的な物語形式を引き出すため、逃れられない社会的および言語的な次元があることを示唆しています。私が誰であるかは、部分的には私が聞いた物語、私に割り当てられた役割、他者と共有した自伝によって決まります。この視点は共感を育むことができます:誰かを理解することは、その人の物語を聞くことに似ており、人々の間の対立はナラティブの衝突として見ることができます。
- 主体性と道徳的責任: 自己が物語であるなら、それは私たちの行動に対する著者意識にどのような意味を持つのでしょうか?一方で、ナラティブセルフは人を選択する主人公として描くことで主体性の感覚を強化します。人々はしばしば、自分自身を意図や理由を持つ者として描く物語を構築し、それが主体性の感覚をサポートします(「私は…だからXをすることに決めた」)。ナラティブはしたがって、主体性と目的の一貫した感覚を強化することができます:私の人生の物語はどこかに向かっており、私の価値観や目標によって導かれています。しかし、神経科学の発見(ガザニガのインタープリターのような)によれば、この主体性の物語の多くは事後のフィクションかもしれません—私たちの脳は時には行動し、その後に私たちのナラティブ機能が理由を作り上げます。これは、私たちが大切にしている意識的な主体性の感覚が、少なくとも部分的には、ナラティブモジュールによって作り出された幻想である可能性を示唆しています。心理学者のダニエル・ウェグナーは、意識的な意志の感覚は、行動を説明するために脳が「物語を語る」ことであり、行動の実際の原因ではないと有名に主張しました。もしそうであるなら、ナラティブセルフ理論は、主体性に対するより謙虚な見方を促すかもしれません:私たちはある意味で事後の語り手であり、無意識のプロセスから生じた行動に対して功績を取っているのです。それにもかかわらず、私たちが作り出すナラティブは将来の行動に影響を与えることができます—例えば、私が自分を「勤勉な学生」として語るなら、その物語に従って行動するかもしれません。倫理において、ナラティブ思考は、良い人生を送ることが良い物語を著すこと、つまり自分が誇りに思える物語であり、他者の物語を尊重するものであることを示唆します。それは人生をテーマ、キャラクターの発展、ナラティブの一貫性(例えば、自分が物語の中でなりたいキャラクターの一貫性を確保すること)という観点で見ることを奨励するかもしれません。
- 記憶と学習: ナラティブの視点は、自己のアーカイブとしての記憶の重要な役割を強調します。記憶することは単にデータを保存することではなく、現在のアイデンティティに意味を持たせる過去を積極的に構築することです。これにより、記憶がしばしば自己奉仕的である理由が説明されます:私たちは現在のナラティブをサポートする記憶を強調し、そうでないものを軽視したり忘れたりします。また、記憶の問題に対する治療法を示唆しています:例えば、断片的な記憶を持つ人(PTSDのような)をナラティブ的に統合することで、その破壊的な力を減少させることができます。教育は、学生が新しい知識を物語の文脈に置くことで、ナラティブを活用することができます。これは理解と保持を改善する傾向があります(私たちの脳は自然に物語に引きつけられるため)。しかし、ナラティブの一貫性を優先するために、私たちの記憶は歪曲されやすくなります—私たちは好ましい自己イメージに合うように歴史を「書き直す」かもしれません。これは法的および個人的な結果を持ちます(例えば、偽の記憶は、もしそれが自分のナラティブに合うなら、本当のように感じられるかもしれません)。ナラティブセルフを理解することは、自分の記憶された人生の物語に対してより批判的になることを奨励します:これは本当に起こったことなのか、それとも私はナラティブ化しているのか?そして、異なる人々が同じ出来事について異なるナラティブを持つ可能性があることを認識します(例えば、家族が共有した出来事を自伝の中で異なるように思い出す)。
- 意識と自己感覚: おそらく最も深い影響は意識そのものにあります。多くの研究者は現在、意識の流れを実際にはナラティブの流れと見なしています。私たちの意識は客観的な現実を受動的に受け取るのではなく、進行中の物語に合うように経験を積極的に解釈し編集します(「私」を中心としたナラティブ)。この意味で、意識はナラティブの生産です。ガザニガが言ったように、意識は脳のモジュールが競い合い、「インタープリター」が勝利した出力を物語に統合することから生じます。もしナラティブセルフ理論が正しいなら、「私」であることの感覚は本質的に語り手であり、同時に物語であることです。それは、自己が精神的な出来事を観察するという伝統的な二元論を解消します—代わりに、自己はこれらの出来事から生じるナラティブ構造です。これは、自己の構築された性質を認識することが解放につながるか、少なくとも自分の考えとのより健康的な関係をもたらす可能性があるという仏教やヒュームの考えと一致するかもしれません(それらを絶対的な現実ではなく、物語の一部として見る)。一方で、それは存在論的な質問を提起します:「私」が単なる物語であるなら、誰がその物語を語っているのか?物語の外に「私」は存在するのか?ナラティブ理論家は、物語と語り手は一つのプロセスであり、互いに反射的に創造し合っていると言うでしょう。意識は、脳の物語を語る劇場として見ることができ、自己の障害(解離性同一性障害や統合失調症のような)は、ナラティブの統合における乱れ(複数の競合する物語や一貫性のないナラティブ)として見ることができます。
学際的な統合#
ナラティブセルフの概念は、このようにして異なる学問分野の豊かな交差点となっています。哲学者は、「自己」がナラティブであることの意味について概念的な明確さを提供します(例えば、個人的なアイデンティティを単なる記憶の連続性から区別し、自己物語の倫理的次元を提起する)。心理学者は、人間が実際にどのようにナラティブを自己構築に利用し、それが幸福や認知にどのように関連するかについての実証的な研究を提供します。神経科学は、脳がナラティブプロセスをどのように実装するかのメカニズムを提供します(例えば、記憶システムやDMNの統合活動を通じて)。文学理論は、ナラティブの構造、プロット、視点の理解を提供し、人生の物語に比喩的に適用することができます(例えば、自己概念における語り手、英雄、敵役の役割)。人工知能やロボティクスでさえ、自己のナラティブモデルに関与しています(例えば、将来の行動を予測するために「自己物語」を維持するAIの設計)。
要するに、自己が基本的にナラティブであるという命題は、私たちの内省的な経験と共鳴し(私たちはしばしば自分自身について物語を紡いでいると感じる)、多くの理論と証拠の収束する線によって支持されているため、広く支持を得ています。それは、私たちが時間を超えて統一感を達成する方法、人生の出来事に意味を見出す方法、他者に自分が誰であるかを伝える方法を説明する強力な枠組みを提供します。しかし、それは自己のすべての側面がナラティブであるわけではなく、すべての人が同じ程度にナラティブに依存しているわけではないという注意によっても和らげられています。したがって、ナラティブセルフは、アイデンティティを理解するための説得力のあるモデルとして最もよく見られます—それは物語を語る心を強調し、新しい質問を開きます。私たちは自分の物語の著者なのか、それとも無意識のキャラクターなのか?私たちの物語はどれほど柔軟なのか?そして、自己のナラティブをどの程度まで書き直すことができるのか?これらの質問は、人文学、社会科学、神経科学の研究と議論を刺激し続け、ナラティブセルフが活気ある学際的なトピックであり続けることを保証しています。
結論#
自己のナラティブ的性質は、さまざまな分野での多面的な解釈とともに、人間のアイデンティティに対する理解を豊かにします。それは、自分自身(または他者)を知ることが、主に語られている物語を理解することであることを示唆しています。私たちの記憶、人格、さらには脳のプロセスさえも、私たちの人生に形を与えるナラティブ構築の行為に参加しています。この考えを受け入れるか、挑戦するかにかかわらず、デネットやリクールの肯定からストローソンの懐疑的な視点まで、生成された対話は、私たちが誰であるかについての現代の理解を間違いなく深めました。結局のところ、ナラティブセルフは理論であり、適切に言えば物語でもあります:私たちがどのようにして私たちがなるのか、そして私たちが経験する人物について、学者たちが共同で書いている物語です。
参考文献#
- Dennett, Daniel C. (1992). “The Self as a Center of Narrative Gravity,” in F. Kessel, P. Cole, & D. Johnson (Eds.), Self and Consciousness: Multiple Perspectives. Hillsdale, NJ: Erlbaum. (Philosophy / CogSci). https://www.researchgate.net/publication/28762358_The_Self_as_a_Center_of_Narrative_Gravity
- Ricoeur, Paul (1991). “Narrative Identity.” Philosophy Today 35 (1): 73–81. (Philosophy / Hermeneutics). https://archive.org/download/paulricoeurtheconceptofnarrativeide/Paul_Ricoeur_the_Concept_of_Narrative_Ide.pdf
- McAdams, Dan P. (1993). The Stories We Live By: Personal Myths and the Making of the Self. New York: Guilford Press. (Psychology). https://www.amazon.com/Stories-We-Live-Personal-Making/dp/1572301880
- Bruner, Jerome (1987). “Life as Narrative.” Social Research 54 (1): 11–32. (Psychology). https://ewasteschools.pbworks.com/f/Bruner_J_LifeAsNarrative.pdf
- Schechtman, Marya (1996). The Constitution of Selves. Ithaca, NY: Cornell University Press. (Philosophy). https://www.amazon.com/Constitution-Selves-Marya-Schechtman/dp/0801474175
- Strawson, Galen (2004). “Against Narrativity.” Ratio 17 (4): 428–452. (Philosophy). https://lchc.ucsd.edu/mca/Paper/against_narrativity.pdf
- Gazzaniga, Michael S. (2017). “Interaction in Isolation: 50 Years of Split-Brain Research.” Brain 140 (7): 2051–2053. (Neuroscience). https://academic.oup.com/brain/article/140/7/2051/3892700 (Note: See also Gazzaniga’s books like The Consciousness Instinct (2018) or Who’s in Charge? (2011) for broader discussion of the interpreter).
- Buckner, Randy L.; Carroll, Daniel C. (2007). “Self-Projection and the Brain.” Trends in Cognitive Sciences 11 (2): 49–57. (Neuroscience). https://www.prospectivepsych.org/sites/default/files/pictures/Buckner-and-Carroll_Self-projection-and-brain-2006.pdf
- Damasio, Antonio R. (1999). The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness. New York: Harcourt Brace. (Neuroscience). https://ayanetwork.com/aya/psyche/The%20Feeling%20of%20What%20Happens%20Body%20and%20Emotion%20in%20the%20Making%20of%20Consciousness%20by%20Antonio%20Damasio%20%28z-lib.org%29.epub.pdf
- Metzinger, Thomas (2003). Being No One: The Self-Model Theory of Subjectivity. Cambridge, MA: MIT Press. (Philosophy / Neuro). https://skepdic.ru/wp-content/uploads/2013/05/BeingNoOne-SelfModelTheoryOfSubjectivity-Metzinger.pdf
- Bartlett, Frederic C. (1932). Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology. Cambridge: Cambridge University Press. (Experimental Psych). https://pure.mpg.de/pubman/item/item_2273030_5/component/file_2309291/Bartlett_1932_Remembering.pdf
- Wegner, Daniel M. (2002). The Illusion of Conscious Will. Cambridge, MA: MIT Press. (Psychology). https://archive.org/details/illusionofconsci0000wegn
- Pennebaker, James W. (1997). Opening Up: The Healing Power of Expressing Emotions. New York: Guilford Press. (Clinical Psych). https://nwkpsych.rutgers.edu/~kharber/healthpsychology/READINGS%202024/Pennebaker.%20Opening%20Up.pdf
- White, Michael; Epston, David (1990). Narrative Means to Therapeutic Ends. New York: W. W. Norton & Company. (Therapy). https://josefaruiztagle.cl/wp-content/uploads/2020/09/Michael-White-David-Epston-Narrative-Means-to-Therapeutic-Ends-W.-W.-Norton-Company-1990-1.pdf
- MacIntyre, Alasdair (1981). After Virtue: A Study in Moral Theory. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press. (Philosophy / Ethics). https://epistemh.pbworks.com/f/4.%2BMacintyre.pdf
- Locke, John (1690). An Essay Concerning Human Understanding. (Philosophy). https://www.gutenberg.org/ebooks/10615 (See Book II, Chapter XXVII).
- Hume, David (1739). A Treatise of Human Nature. (Philosophy). https://www.gutenberg.org/ebooks/4705 (See Book I, Part IV, Section VI).
- Gallagher, Shaun; Zahavi, Dan (2008). The Phenomenological Mind: An Introduction to Philosophy of Mind and Cognitive Science. London: Routledge. (Phenomenology / CogSci). https://dl.icdst.org/pdfs/files/45cd446f868f4230dc4e3546e97a5df7.pdf
- Velleman, J. David (2005). “The Self as Narrator,” in Self to Self: Selected Essays. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. (Philosophy). https://web.ics.purdue.edu/~drkelly/VellemanSelfAsNarrator2005.pdf
- Sacks, Oliver W. (1985). The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical Tales. New York: Summit Books. (Neurology / Lit). https://web.arch.virginia.edu/arch542/docs/reading/sackspdf/sacksvl.pdf (See Preface).
FAQ#
Q 1. 「ナラティブセルフ」の核心的な考え方は何ですか? A. 核心的な考え方は、個人的なアイデンティティが固定されたものではなく、私たちが構築し、修正し、人生について語る進行中の物語や自伝であり、経験、記憶、解釈を統合して、時間を超えた一貫した自己感覚を作り出すというものです。
Q 2. この理論に関連する主要な人物は誰ですか? A. 重要な思想家には、哲学者ダニエル・デネット(「ナラティブ重力の中心」)、哲学者ポール・リクール(「ナラティブアイデンティティ」)、心理学者ダン・マクアダムス(「ライフストーリー」)、心理学者ジェローム・ブルーナー(「ナラティブモード」)、神経科学者マイケル・ガザニガ(「左脳インタープリター」)が含まれます。
Q 3. ナラティブセルフ理論の主な批判は何ですか? A. 哲学者ガレン・ストローソンが主要な批判者です。彼はナラティブセルフの普遍性に反対し、一部の人々(「エピソディック」)は自分の人生を連続した物語として経験せず、強いナラティブフレームワークなしで完全に有効な生活を送っていると主張しています。「ディアクロニック」な個人とは異なります。彼は、人格や幸福のためにナラティビティを要件として課すことに対して警告しています。
Q 4. 神経科学はナラティブセルフの考えをどのように支持していますか? A. ガザニガの分離脳研究のような研究は、私たちの行動に対して常に説明(ナラティブ)を作り出す「左脳インタープリター」を示唆しています。デフォルトモードネットワーク(DMN)に関する研究は、自己参照的思考や記憶の想起中に活性化し、過去、現在、未来の自己概念を統合する「内部ナラティブ」を生成する可能性があることを示しています。
Q 5. この理論の実際的な影響は何ですか? A. それは、アイデンティティを動的なものとして理解し、主体性を構築されたものとして理解し、記憶を再構築的なものとして理解することに影響を与えます。治療的な応用(例えば、ナラティブセラピーは人生の物語を「再著作」することを奨励します)や倫理への影響(良い人生を送ることは一貫した、道徳的な物語を著すこと)があります。