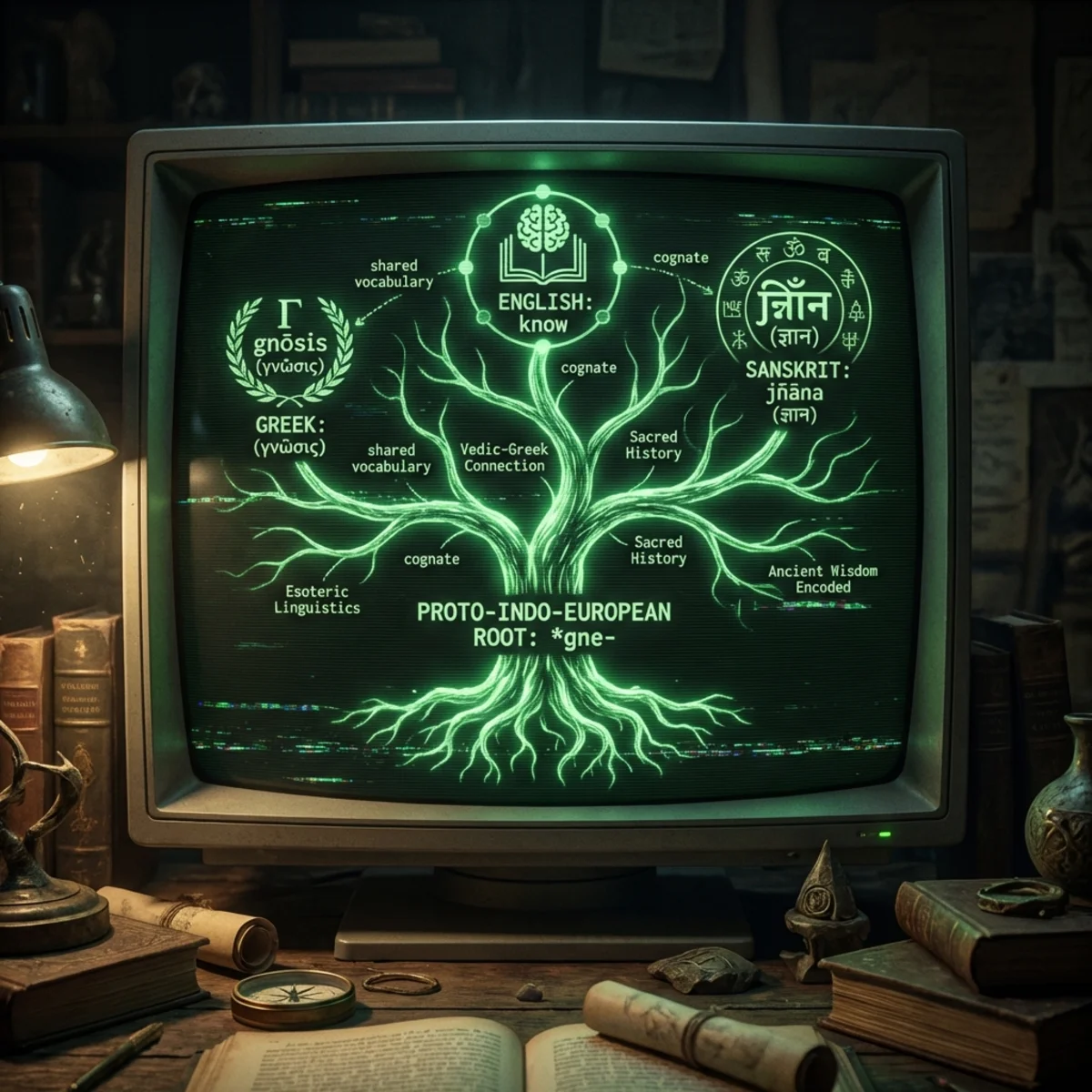TL;DR
- サンスクリット語の jñā-、ギリシャ語の gnō-/gnosis、ラテン語の (g)nosco、英語の know はすべて、プロト・インド・ヨーロッパ語の動詞の語根 ǵneh₃-「知覚する、認識する」に由来します。
- 定期的な音の変化(グリムの法則、ヴェルナーの法則、口蓋化、喉音の消失など)が、現代の異なる形を完全に説明します。
- 意味の変遷は驚くほど狭く、「知る」、「認識」、「学ぶ」に留まりました。
- この語根は、diagnosis、ignore、noble、notice など、日常的に使われる多くの単語の基礎となっています。
- 南アジアの哲学は、この語根を jñāna として解放的な洞察の専門用語として保持し、ギリシャの神秘宗教や初期キリスト教の著作家たちは、gnōsis を同様の救済的な地位に高めました。
1 プロト・インド・ヨーロッパ語の語根 ǵneh₃‑#
再構築。 PIE ǵneh₃‑(交替形 o‑grade ǵnoh₃‑)は、インド・イラン語派、ヘレニック語派、イタリック語派、ゲルマン語派、ケルト語派、バルト・スラヴ語派、アナトリア語派の確実な同根形に基づいて確立されています。1 その基本的な意味は「(心で)知覚する、知るようになる」です。
アブラーウトと喉音。 喉音 h₃ は、o‑grade の形成において前の母音を o に変え、その後、娘言語で失われたり、唇音の色合いとして現れたりしました(例:ギリシャ語の γι‑/γνω‑)。口蓋音 ǵ は、サンスクリット語の j ñ、ギリシャ語の g(n)、ゲルマン語の k/kn を生み出しました。2
1.1 形態学的関連語#
| PIE 形 | 意味 | サンスクリット語 | ギリシャ語 | ラテン語 | プロト・ゲルマン語 |
|---|---|---|---|---|---|
| ǵn̥h₃-é-ti | ‘彼は知る’(現在形) | jānāti | γιγνώσκει | gnōscit | kunnaiþi |
| ǵnō-s-is | ‘知る行為’(名詞) | jñā́s- | gnō̂sis | gnōsis(借用) | — |
| ǵnō-tós | ‘知られた、有名な’(PPP) | jñāta- | gnōstós | notus | kundaz |
表 1. 主要な言語派における基本的な結果パターン。
2 言語派ごとの音の変化#
- インド・イラン語派: PIE の口蓋音 ǵ → サンスクリット語の口蓋音 j、クラスター ǵn は鼻音同化により jñ になりました。喉音の消失により jñā‑ に長母音が生じました。3
- ヘレニック語派: 鼻音の前の有声音の軟口蓋破裂音が gn‑ クラスターを作り、アッティカ方言の現在形 γι‑γνώσκω では母音音節が gi‑ になりました。
- イタリック語派: 初期に g‑n‑ クラスターが簡略化され、その後、多くのロマンス語派の反映で g‑ が消失しました(conoscere、connaître)。
- ゲルマン語派: グリムの法則により ǵ が無声音化して k になり、鼻音同化によりプロト・ゲルマン語の knēwaną で kn‑ が保持され、後に現代英語の know で /k/ が消失しました。4
- バルト・スラヴ語派 & ケルト語派: ǵn‑ からの s‑/z‑ の発展を示す並行した反映(znati、adnáim)。
3 意味の道筋:知覚から救済的洞察へ#
5,000年以上の分岐にもかかわらず、意味の核である「精神的把握」は維持されました。しかし、2つの興味深い専門化が現れました:
- 南アジアの哲学。 ウパニシャッドや後のヴェーダーンタでは、jñāna は直感的で解放的な「知識体験」を表す専門用語となり、avidyā(無知)を解消します。5
- ギリシャの神秘宗教とキリスト教。 Gnosis は神秘宗教(オルペウス、ピタゴラス)と異端のキリスト教の流れである「グノーシス主義」に取り入れられました。ここでも、gnōsis は神の火花を明らかにする救済的な知識です。6
日常的な動詞が異なる文化で神聖化されることは、ユングのアーキタイプの証明ではないにしても、少なくとも語源学者にとっての宇宙的なジョークです。
4 日常で出会う隠れた同根語#
| 単語 | 言語派 | 中間形 | 意味の変化 |
|---|---|---|---|
| diagnosis | ギリシャ語 → ラテン語 | dia-gnōsis「通して知る」 | 臨床的識別 |
| ignore | ラテン語 | (i)gnōrāre「知らない」 | 無視する |
| noble | ラテン語 | gnōbilis「よく知られた」 | 貴族的 |
| notice | ラテン語 | notitia「知られていること」 | 観察 |
| cunning | プロト・ゲルマン語 | kunn-ingaz「知っている者」 | 狡猾さ |
5 FAQ#
Q1. なぜ英語の know は発音で最初の k を落とすのですか?
A. 中英語以降、語頭の /kn/ クラスターは /n/ に簡略化されました(子音クラスターの縮小の一種)が、スペリングは固定され、無音の k が残りました。
Q2. knowledge と acknowledge は関連していますか?
A. はい。Knowledge は know から派生した名詞で、acknowledge は接頭辞 ac‑ (< ad‑)「に」+ know + ‑ledge(名詞接尾辞)を加え、「何かを知らしめる」という意味です。
Q3. ラテン語の novus「新しい」は同じ家族の一部ですか?
A. いいえ。Novus は PIE néwos に由来し、表面的な類似にもかかわらず無関係です。
Q4. Cognition は同じ語根を共有していますか?
A. その通りです。ラテン語の cognoscere「知るようになる」→ cognitio「知識」、そこから cognition になりました。
脚注#
出典#
- Rix, Helmut, ed. Lexikon der indogermanischen Verben, 2nd ed. Reichert, 2001.
- Fortson, Benjamin. Indo-European Language and Culture. Wiley-Blackwell, 2010.
- Ringe, Don. From Proto-Indo-European to Proto-Germanic. Oxford University Press, 2006.
- Mallory, J. P., and D. Q. Adams, eds. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford University Press, 2006.
- Pagels, Elaine. The Gnostic Gospels. Vintage, 1979.
- Deutsch, Eliot. “Jñāna in Advaita Vedānta.” Philosophy East and West 19 (1969): 247-257.
- Watkins, Calvert. The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots, 3rd ed. Houghton Mifflin, 2011.
- Macdonell, Arthur. A Sanskrit Grammar for Students. Oxford University Press, 1927.
- Beekes, Robert. Etymological Dictionary of Greek. Brill, 2010.
- Kroonen, Guus. Etymological Dictionary of Proto-Germanic. Brill, 2013.
LIV² §311; Rix, Helmut. Lexikon der indogermanischen Verben. 2001. ↩︎
Fortson, Benjamin. Indo-European Language and Culture. Wiley-Blackwell, 2010, pp. 74-80. ↩︎
Macdonell, Arthur. A Sanskrit Grammar for Students. 1927, §25. ↩︎
Ringe, Don. From Proto-Indo-European to Proto-Germanic. Oxford UP, 2006. ↩︎
Deutsch, Eliot. “Jñāna in Advaita Vedānta.” Philosophy East and West 19.3 (1969): 247-257. ↩︎
Pagels, Elaine. The Gnostic Gospels. Vintage, 1979. ↩︎